『刀剣乱舞』はなぜ世界で愛される? ニトロプラス小坂社長が語るIP哲学

リリースから10周年を迎えてもなお、国内外で人気を誇る『刀剣乱舞』。その生みの親であるニトロプラスの小坂社長は、「世界を強く意識したわけではない」と語りながらも、同社の品群は確実に国境を越え、多くのファンを魅了し続けています。
本記事では、独自の視点から人気作を生み出すニトロプラスのIP哲学に迫ります。
国内の「面白い」を追求する創作哲学
― 本日は「世界クオリティのIP戦略」というテーマでお話を伺います。今年で10周年となる『刀剣乱舞』は、構想段階から世界展開を意識されていたのでしょうか。
構想段階ではそこまで意識していませんでした。
というのも、世界展開を意識しすぎると作品作り以外の得意ではない業務にまで力を割かなければならなくなります。それよりも、まずは国内でターゲットとして定めた方向にヒットする「面白い」ものを誠実に作っていくことに注力しました。
その結果を評価して頂けたということであれば、「面白い」という感覚を信じ、目の前のお客様や時代の空気にしっかりと向き合って、作品作りに集中することが、結果的に世界展開へと繋がる道を切り開いてくれるのかもしれません。
私がコンテンツ作りで目指すのは、自分が納得できるものを作り、誰かの人生を少しでも豊かにすることです。私自身もそういった、人生を変えるようなコンテンツに出会ってきましたから、今度は送る側として感動を届けたい。そして、出会った方がまた送り手となって、脈々と繋がっていくことに強く興味があります。
この思いは、高校時代に同人誌活動を通じて、創作の楽しさやファンとの繋がりを学んだことが原体験。そのまま今のニトロプラスの風土に繋がっています。
「それぞれの本丸」が育む熱量
― ファンが送り手になるという循環は、熱量が伝播していく上で重要ですね。ファンの熱量を維持し、さらに広げていくために、特に重視されていることは何ですか?
ニトロプラス創立以来ずっとそうやって来ましたが、まず、自分自身が作品に対して誠実であろうという気持ちで、今できる最大のエネルギーを注ぐこと。そして、出来上がった作品に対して、自分自身がファンであるという気持ちで向き合うこと。この姿勢こそが、ファンからの信頼を得るブランディングの基礎だと思っています。
この想いを胸に『刀剣乱舞』に関しては、“想像の余地”を大事にしています。
各プレイヤーが「このキャラクター同士はどうなるんだろう」「なぜこういう性格なんだろう」などと考察したり、物語の隙間を想像したりする楽しみですね。それが創作の原点であり、力になると信じています。
その考え方が最もよく表れているのが、本作の「それぞれの本丸※1」という概念です。プレイヤーごとに集めている刀剣男士も、部隊も、出陣先も違うため、一つとして同じ本丸はありません。
※1 本丸:プレイヤーがゲーム内で拠点とする場所のこと
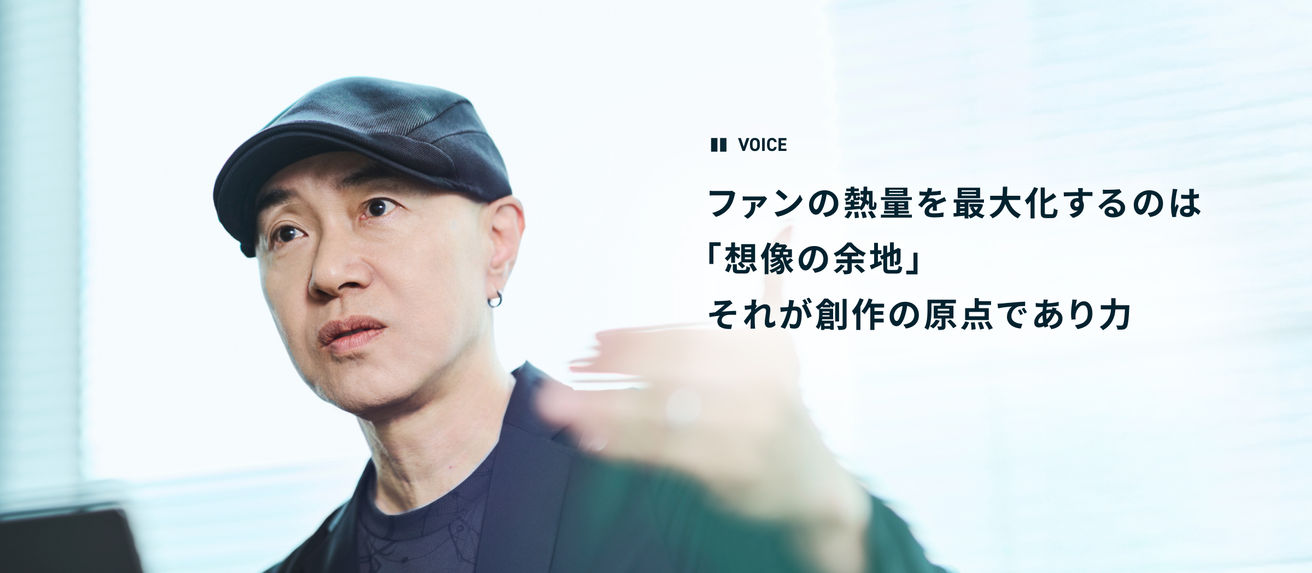
イラストレーター、書籍編集者、玩具デザイナー、ゲームデザイナーなどエンターテイメントに関わる様々なクリエイティブに従事した後、2000年にニトロプラスを設立。脚本家である副社長の虚淵玄をはじめ、社内外のクリエイターらと幅広いコンテンツの制作やオリジナルIPを多数生み出している。
アニメ、演劇、実写映画といった多様なメディアミックス展開は、その延長線上に「こんな本丸もあるんだよ」という新しい視点の提案となればいいなと考えています。
題材とした日本の刀剣が長寿であるように、『刀剣乱舞』も長寿コンテンツでありたいと願っています。
この、「それぞれの本丸」という考え方をベースとしたメディアミックスは、展開の幅を広げ、コンテンツの長寿を支える大きな要因にもなっています。
同じ食べ物でも調理法を変えれば新しい味に出会えるように、私たち自身も発見を楽しみながら、ファンに常に新鮮な驚きを提供したいですね。無節操にやっているように見えるかもしれませんが、一つひとつを丁寧に精査し、時には調整を重ねながら、プロデュースできる範囲を広げています。
そうすることで、たとえ一時的に離れることになっても何かのきっかけで再燃してもらえることもある。そんな風に、幅の広い、息の長いIPであり続けたいと思っています。
世界に「刺さる」日本のコンテンツの強みとニトロプラスの独自性

写真左 虚淵氏 写真右 小坂氏
― ニトロプラスのコンテンツには国内外に多くのファンがいますが、その反響や手応えをどう感じていますか?
日本のコンテンツは、国内だけでなく世界中に刺さる、普遍的な魅力を持っていると確信しています。
例えば、日本の人口で3%のニトロプラスのファンがいるなら、世界にも同じ比率でファンがいる、という感覚です。つまり、日本の文化や背景を知らなくても、普遍的な“好き”という感情に訴えかける魅力があると感じています。
実際、副社長の虚淵玄がシナリオを生み出した『魔法少女まどか☆マギカ』や 『PSYCHO-PASS』などでも海外からのイベントオファーをいただき、世界各地を訪れました。そこで驚いたのは、海外展開していないはずの我々のゲームで日本語を覚えたという方やニトロプラスコンテンツのキャラクターに扮したコスプレイヤーがどこの国にもいたりすることです。
私たちが特に海外を意識せずに作った作品から、これほど強い、推し活の原動力が生まれている。人間の本質的な“好き”という感情は国境を越えて共通している証拠だと感じました。
― そのような中で、日本のコンテンツが海外で幅広く受け入れられる背景には、どのような強みがあるとお考えですか?
まず、日本のコンテンツの強みは、文化が途絶えず熟成されてきた長い歴史にあると考えています。平和な時代が長く続いたことで、エンターテインメントが深く発展し、漫画やアニメといった現代の表現へと繋がっています。
そして、日本人はコミュニケーションにおいて相手の意図を想像し、行間を読む力に長けていると感じます。この想像力は、コンテンツ作りにおいても非常に重要です。登場人物の感情を想像し、客観的に物語を動かしたりする上で不可欠だからです。

日本のコンテンツ作りは世界的に見てかなり特殊です。多彩で複雑で深いコンテンツが多い。
その中でもニトロプラスの作品は、意外な切り口から独自性を発揮したり、過去のコンテンツの文脈を独自に読み解いて応用したりして個性を出している作品が多い。
インターネットや動画配信の普及により、海外の人々もそうした奥深さに触れ、面白さに気づき始めているのだと思います。
― 2025年4月発売のアクションゲーム『Dolls Nest』がSteamの売上ランキング上位にランクイン※2し、ユーザーレビューでも高評価を得ています。
Steamの特性である海外向けのプラットフォームという点は意識してはいますが、本作の原案/ディレクションの太田が構築する独自の世界観が、国内外問わず多くの人々に響くと信じてリリースしました。
メカ少女のカスタマイズ性や探索型アクションとしてのボリューム感が高く評価されている点は、非常に嬉しいですね。少し硬派なゲーム性も多くの方に受け入れていただけたようで何よりです。
結果として予想以上に日本での支持が厚く、海外には大きな伸びしろを感じています。海外プロモーションはまだ手探りですが、ユーザーからの高評価に期待し、サイバーエージェントの宣伝部とも連携しながら、効果的な戦略を探っていきます。
※2 日本国内Steam売上ランキング5位(2025年4月24日時点)
IP成長の鍵は「変化と不変」を見極めること
─ サイバーエージェントグループに参画されて約1年が経ちました。
ミュージカル『刀剣乱舞』でネルケプランニングさんと連携するなど、グループ入り前から多方面との協業はありました。参画後は、ビジネス展開で大きな助力をいただいていますし、私たちがIPを作るお手伝いをすることで、お互いに足りない部分を補い合えればと考えています。
私たちのクリエイティブと、グループの持つ多様な強みを組み合わせれば、これまで以上に大きなスケールで世界中に驚きと喜びを届けられる。その可能性に、今まさにワクワクしているところです。

─ では最後に、今後の展望についてお聞かせください。
『刀剣乱舞』をはじめとする私たちのコンテンツを、今後さらに長く、既存のファンはもちろん、世界中のファンに愛されるIPへと育てていきたいです。そのために重要なのが、「作品の変えてはいけない本質」は守りながらも、時代の変化に合わせて「柔軟に変える部分」を的確に見極めること。
そのために私をはじめ当社のスタッフは常に世の中の繊細な流れを感じ取り、変化に対応する方法を模索しています。時代に合わせること、敢えて合わせなかったり逆張りをすることなど、多彩な手段をバランスよく繰り出していきたいです。
─ 世界展開を進める中で、戦略的に特に重要とする国やエリアはありますか?
特定の文化圏に限定せず、普遍的な面白さを追求し、より幅広い層へのアプローチ方法を模索していきます。
そして、ビジネス戦略を超えた個人の想いとしては…様々な事情で心が休まらない状況にいる人々にこそ、私たちの作る物語が届けばと願っています。
人間の心には、時にダークな物語を求める側面もありますが、それはあくまでフィクションの中で、安全に楽しむべきものです。現実の世界で誰かが傷つくのではなく、物語を通して多様な経験をすることで、人は優しくなれたり、現実を生きる力をもらえたりすることがある。
私たちの作るコンテンツが、困難な状況にある人々の心に、一時でも安らぎや希望をもたらすことができるなら、クリエイターとしてそれ以上の喜びはありません。

記事ランキング
-
1

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像
サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像
サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像
-
2

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...
社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代
社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...
-
3

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...
-
4

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく聞かれる質問10...
「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく聞かれる質問10選に人事マネージャーがお答えします
「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく...
新Developer Expertsが語る、バンディットアルゴリズムのさらなる可能性

当社には、特定の分野に抜きん出た知識とスキルを持ち、第一人者として実績を上げているエンジニアを選出する「Developer Experts制度」があります。AIを武器に、事業インパクトに直結する成果を出すエンジニアの育成をさらに強化すべく、AI Driven Development、AI Ops、AI基盤の3つを新たな注力技術領域として策定いたしました(参照:「2028年までに全社の開発プロセスを自動化する。サイバーエージェントAI活用のこれまでとこれから」)。
この度、AI基盤のバンディットアルゴリズムにおける初のDeveloper Expertsに選出された「AI Lab」所属の蟻生に、当技術の持つ魅力やさらなる応用の可能性、今後の自身の展望など話を聞きました。







