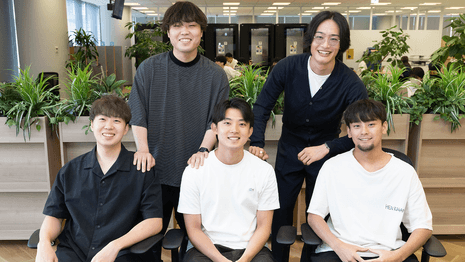CVR3.4倍を実現したSmart Targeting
~AJAが挑む動画広告の効果最大化~

動画広告市場は急成長していますが、ブランド広告には投資対効果が見えづらいという課題がありました。
当社グループの(株)AJAが提供する、コネクテッドTVに特化した動画広告プラットフォーム「インクリー」は、この課題にデータとAIで挑んでいます。2024年8月にリリースした「Smart Targeting」では、従来の年齢・性別といった区分ではなく、ユーザー一人ひとりのコンバージョン可能性を機械学習で推定。広告効果が大幅に向上し、従来比3.4倍の成果を記録した事例も生まれています。
プロダクト責任者の松岡とデータサイエンティストの中村に、1年半で開発した技術の裏側と、プライバシー時代の次なる挑戦、そして変化対応力を支える組織のありかたを聞きました。
Profile
-

松岡 竜也 (株)AJA DSP Division
2019年新卒入社。(株)AbemaTVの広告営業としてキャリアをスタート。入社3年目にAJAに異動し、新規プロダクトの立ち上げ責任者、「インクリー」の営業マネージャー、カスタマーサクセスチームの立ち上げを経て現在は「インクリー」のプロダクト責任者を担当。 -

中村 優太 メディア統括本部 Data Science Center(DSC)機械学習エンジニア
2024年新卒入社。メディア統括本部 Data Science Center(DSC)に所属し、AJA DSPの広告リクエストのデータ分析や、機械学習を用いた広告効果最適化ロジックの開発など、MLOps領域を中心に担当。
動画広告効果の可視化と最適化へのAJAの取り組み
── 動画配信サービスが普及する中で、広告市場にはどのような変化が起きていますか。
松岡:認知度向上を目的とするブランド広告には、テレビや屋外広告といったオフライン媒体が中心で効果測定の手段が限られていたため、投資対効果が見えづらいという長年の課題がありました。
この状況が変わり始めたのが「ABEMA」をはじめとした動画配信サービスの普及です。デジタルであるがゆえに、誰が、いつ、どの広告を見たのかというデータが取得できるようになりました。データに基づいた効果測定が可能になり、ブランドコミュニケーションができるリッチな広告を、効果を見ながら配信できる環境が整ってきたのです。このように、動画広告市場は急速に成長しています。
AJAでは、サイバーエージェントがメディア運営で培ったノウハウと技術力を強みに、こうした市場の変化に対応した広告プロダクトを開発・提供しています。厳選したプレミアムメディアでブランドセーフティに配慮した動画広告配信を行い、安心・安全で効果的なプロモーションを実現しています。
中でも現在注力しているのが「インクリー」です。「インクリー」は「ABEMA」など動画配信サービス向けの広告配信に特化したプラットフォームで、広告効果の可視化と最大化に取り組んでいます。
そして2024年8月「インクリー」に新機能「Smart Targeting」を追加しました。この機能により、広告から実際の購入や登録などの行動につながる割合を示すCVRが、従来の配信方法と同月で比較して3.4倍に向上した事例も出ています。
── 広告効果の可視化が実現したとして、次の課題は何でしょうか。
松岡:動画配信サービスへの広告出稿が当たり前になってきた今、次の課題は「どのように配信すれば効果が上がるのか」という最適化です。
それまでは、広告配信の設定や効果分析を手動で行っていたため、効率が悪く人手もかかっていました。そこで、AIや機械学習を活用して自動化する必要があると考え、2024年にData Science Center所属の中村がチームに参画しました。
中村:参画して実際にデータを見てみると、ユーザーの広告視聴時間帯や性別・年齢といった属性情報、視聴デバイスなどの行動履歴データに加え、広告素材に関するデータなど、多様なデータがあり、動画広告で扱えるデータの種類の豊富さに驚きました。データ活用への関心が組織全体で高まっており、分断していたデータを統合して、より大きな価値を生み出していこうという動きが加速しています。
── データ活用の将来的な展開として、どのような取り組みを考えていますか。
松岡:今、仮説として進めているのは、コンテンツとクリエイティブの最適な組み合わせを見つけることです。例えば、同じ30代男性でも、恋愛ドラマを見ている時とスポーツを見ている時では、興味関心が異なります。同じ商品でも、見せるべき広告クリエイティブを変えた方が効果的です。視聴しているコンテンツの文脈に合わせた広告配信に特化した手法を深掘りしていきたいと考えています。
中村:技術的には十分に実現可能です。コンテンツ情報とユーザー情報を組み合わせて、最適な広告クリエイティブを動的に選択する仕組みを構築できます。たとえば、Contextual Banditのような手法を用いれば、視聴しているコンテンツの文脈に合わせて最も効果的な広告をリアルタイムに最適化することも可能です。実用化のためには、ユーザーが視聴しているコンテンツ情報を媒体から提供してもらう必要があります。この協力体制をどう築いていくかが今後の課題です。

Smart Targeting開発の技術的挑戦と次なる展開
── 「Smart Targeting」とは、どのような機能でしょうか。
中村:「Smart Targeting」は、広告効果を最大化するためにターゲティングを最適化する機能です。例えば、マッチングアプリの広告において、従来の配信方法では、過去の実績から「マッチングアプリは20代・30代男性に配信すると効果が良い」という経験則や分析結果に基づいて、年齢や性別といったデモグラフィック属性単位でターゲティングしていました。
しかし、20代の中にもマッチングアプリに興味がない人はいますし、40代でも興味がある人はいます。デモグラ単位で配信すると、興味のない人にも配信してしまう一方、興味のある人を取りこぼしてしまいます。
「Smart Targeting」では、デモグラという大きな区分ではなく、ユーザー一人ひとりが購入や登録などコンバージョンする可能性を推定し、見込みの高い人に配信することができます。
── 開発で工夫した点を教えてください。
中村:広告リクエスト情報だけでは使えるデータが限られているため、ユーザーの広告視聴時間帯や視聴デバイス、属性情報や過去の行動履歴など、さまざまな情報を組み合わせた260次元の特徴量を構築しました。これにより、ユーザーの多様な行動パターンを表現し、モデルの予測精度を高めています。さらに、キャンペーンごとに重要な特徴量を、L1・L2正則化の罰則項でバランスよく選択・抑制することで、スパース化しすぎない安定した特徴量表現を保ち、さまざまな広告配信にも適応できる汎用的な設計を実現しています。
また、学習データの扱いにも工夫が必要でした。広告配信データは時系列データ特有のスパース性や分布の偏りにより扱い方によっては予測精度低下の原因になり得るため、データの密度を保ちながら学習用と評価用に分割する方法を工夫しています。これにより、時間的な偏りを避け、安定したモデル精度を実現しました。
処理方式の選択も重要でした。リアルタイム処理は高速ですが使えるモデルが限定的です。一方、バッチ処理は事前に推論を行うため、より高精度なモデルを使えます。私たちはバッチ処理を採用し、実装コストを抑えながら高精度を実現しました。結果として、バッチ処理で十分な精度が得られることが実証されました。

── 具体的にどのようにユーザーを選んで配信しているのでしょうか。
中村:各ユーザーに対して2つの確率を推定しています。1つは「コンバージョン確率」、もう1つは「その日に動画サービスを訪問する確率」です。広告に触れる可能性がない人に配信しても効果は出ません。この2つを掛け合わせることで、日次で最適なオーディエンスを構築しています。
実際に従来の配信方法と同月で比較したところ、CVR(コンバージョン率)が3.4倍に向上した事例がありました。ユーザー単位でのCV予測モデルを使ったターゲティングの方が、広告効果が高いという結果が明確に出ています。
── ビジネス側とデータサイエンティストがチームで開発することで、どのような成果が生まれましたか。
松岡:大きく2つあります。1つは工数の削減、もう1つは人ではできないレベルの最適化ができるようになったことです。
従来は運用担当者の経験や勘に頼る部分が大きく「Smart Targeting」と同じ事を手動でやろうとすると、広告配信設定を細かく調整して、効果を見て運用するという作業を日々人がやることになります。人である以上、扱える変数の数に限界があります。100個の変数で分析しようと思ったら、100個すべてを調整できる管理画面を用意し、手動で調整し続けなければなりません。
しかし、データとして扱い、機械学習で最適化すれば、そうした制約が取り払われます。それが自動化され、毎日リフレッシュされるようになりました。さらに、効果最適化のための変数の重み付けも自動で分析してくれます。どの変数が重要度が高いかという仮説検証を、人がやるより圧倒的に速く正確にできるようになりました。
── 中村さんは、どのくらいの期間でこの機能を開発したのでしょうか。
中村:AJAに参画して1年半くらいでリリースしました。機能自体の設計・開発期間はおよそ1年ほどですが、それ以前は別のプロジェクトにも携わっていました。開発に着手した当初は、SQLクエリベースの集計により過去の実績から効果の高いセグメントを抽出・分析し、そのセグメントに配信を行う仕組みを構築していました。そこからさらに、機械学習モデルを活用した仕組みへとバージョンアップし、広告効果を一段と高めることができました。
松岡:新機能を開発してリリースまで持っていく際、これまでのAJAでは通常2~3年かかるところを、1年半でリリースできたのは早かったと思います。Data Science Centerの協力と、中村さんのスピーディな開発の賜物と言えます。

未来の広告配信を創るAJAの変化対応力と人材
── 「Smart Targeting」の現在の完成度と、今後の展開について教えてください。
松岡:当初描いていた機能は実装できて効果が出ている反面、運用する中で課題も見えてきました。特に、プライバシー保護の観点から、個人を特定する情報の利用が制限される流れが加速しています。今後、ユーザー単位の最適化だけではカバーできる範囲が限られてしまいます。
そこで、個人を特定しない形での最適化手法が必要になります。その一つが、コンテンツベースでの効果最適化です。視聴しているコンテンツの文脈に基づいて、最適な広告を配信するというアプローチです。
ただ、コンテンツ情報だけだとパーソナライズに比べて精度は落ちます。そこで、クリエイティブの最適化も組み合わせることで精度を高められると考えています。個人情報が利用できる環境ではユーザー単位の最適化、プライバシー保護が優先される環境ではコンテンツとクリエイティブの組み合わせで最適化するというように、状況に応じた手段を用意していきます。
── コンテンツベースの最適化とは、具体的にどのようなものでしょうか。
中村:コンテンツベースの最適化とは、視聴中のコンテンツ内容に応じて最も関連性の高い広告を配信する仕組みのことです。いわゆるContextual Targetingと呼ばれるもので、継続的に取り組んでいるテーマの一つです。例えば、ドラマで俳優がビールを飲むシーンの直後にビール広告を出す、恋愛ドラマの盛り上がるシーンの後にマッチングアプリ広告を配信したりといった形で、コンテンツの文脈と広告の親和性を高め、広告効果を高める試みを行っています。
技術的には、動画からのフレーム抽出・物体検出・OCR・シーン解析・音声認識など、複数の解析技術を組み合わせてコンテンツを理解し、最適な広告を自動選択する仕組みを検証しています。このような手法は技術的には十分実現可能であり、特にVODとの相性が良いです。課題は媒体側からどこまでコンテンツ情報を提供してもらえるかですが、この協力体制が構築できれば、プライバシーを保護しながらも高精度な広告配信が可能になります。
松岡:動画広告市場は成長しており、さまざまなプレイヤーが参入していますが、私たちの強みはメディアとの密接な関係と、日本市場の状況に素早く対応してプロダクトを変えていけることです。「ABEMA」などのメディアと連携しながら、日本市場のニーズに合わせた機能を迅速に開発できます。
── ビジネスとエンジニアが連携してスピーディーに開発できる秘訣は何でしょうか。
中村:その変化対応力を支えているのが、ビジネス職とエンジニア職の距離の近さです。松岡さんと週1でミーティングを行い、戦略や方向性について話し合っています。技術面とビジネス面の両方から今後の方向性を検討し、市場の変化にすぐ対応できる状態を作っています。
入社2年目の私が、プロダクトマネージャーの松岡さんと対等に話し合いながら、「技術的にできるか」「どうやったら実現できるか」「もっとこうした方がいい」といった議論を気軽にできている事自体、貴重な経験です。
松岡:中村さんは営業メンバーや運用担当者とも直接やり取りしてくれるので、頼もしく感じています。開発したものを実際に使ってもらい、そのフィードバックを直接受け取る体制づくりに注力しています。
中村:運用担当者とSlackやミーティングで日常的にコミュニケーションをとれる環境は、プロダクト開発においてすごく進めやすく感じます。「今日はこの予算で配信したい」といった連絡を受けて調整したり、「こういうキャンペーン設計をしたいが技術的に可能か」といった相談を受けたり、頼りにされるので働きがいを感じます。
打った施策に対して「広告効果がすごく良かったです」というコメントを直接いただけることもあれば、効果が悪かった時は営業と一緒に原因を分析し、次の改善策を話し合います。こうした現場との密な連携が、変化対応力につながっていると思います。
── 最後に、AJAやData Science Centerで一緒に働きたい人材について教えてください。
松岡:動画広告市場は今、大きな転換期を迎えています。テレビからインターネットへ、オフラインからオンラインへと広告予算が移り、新しい広告体験が求められています。こうした変化の中で、本当に価値のあるものを提供し、市場を作っていくことに挑戦したい人と一緒に働きたいです。
AJAの魅力は、プロダクト会社であることです。自分たちでソリューションを作り、それを市場に提供して戦える。ビジネス、エンジニア、営業が一体となって価値を生み出せる環境があります。自分たちが価値があると信じるビジョンを、プロダクトという形で実現できることが最大の魅力だと思います。
中村:データサイエンティストとして一緒に働きたいのは、ビジネスKPIを第一に考えられる方です。機械学習やデータサイエンスは手段であって、目的ではありません。ビジネスで求められていることを理解し、それを達成するための最適な手法を考える。たまたまそれが機械学習なら機械学習を使うし、別の手法が適切なら別の手法を選ぶ。そして、どの手法であっても楽しんで実装・検証できる人が理想です。
松岡:市場環境は常に変化しています。その変化に応答し、広告主に価値を届け続けるために、私たちは手を止めません。広告効果という明確な指標で勝負し、それを実証し続ける。そのサイクルを回し続けることが、AJAの強みと言えますね。
記事ランキング
-
1

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像
サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像
サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像
-
2

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...
社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代
社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...
-
3

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...
-
4

「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく聞かれる質問10...
「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく聞かれる質問10選に人事マネージャーがお答えします
「顔採用ですか?」「採用基準を教えてください」など・・ よく...
【対談】ML/DSにおける問題設定術
~ 不確実な業界で生き抜くために ~

機械学習やデータサイエンスがビジネスの現場で当たり前になりつつある今、求められているのは、ビジネスの課題を実装に落とし込み、運用し、継続的な価値を生み出す視点となりつつあります。
サイバーエージェントでは、こうした実践的なスキルを持つ次世代のデータサイエンティストを育成すべく、2025年11月、新卒向け特別プログラム「DSOps研修2025」を実施しました。
「技術を社会実装する際の『問題設定』こそが重要である」 この研修のコンセプトに深く賛同いただき、特別講師としてお迎えしたのが、半熟仮想(株) 共同創業者であり、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」にも選出された齋藤優太氏です。
第1部では、半熟仮想(株) 共同創業者であり、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出された齋藤優太氏をお招きし、「ML/DSにおける問題設定術」について講演いただきました。 続く第2部では、齋藤氏に加え、当社執行役員兼主席エンジニアの木村、AI Lab リサーチサイエンティストの暮石が登壇。「現場視点×経営視点」でパネルディスカッションを実施しました。
本記事では、白熱した第2部「パネルディスカッション」の模様をダイジェストでお届けします。