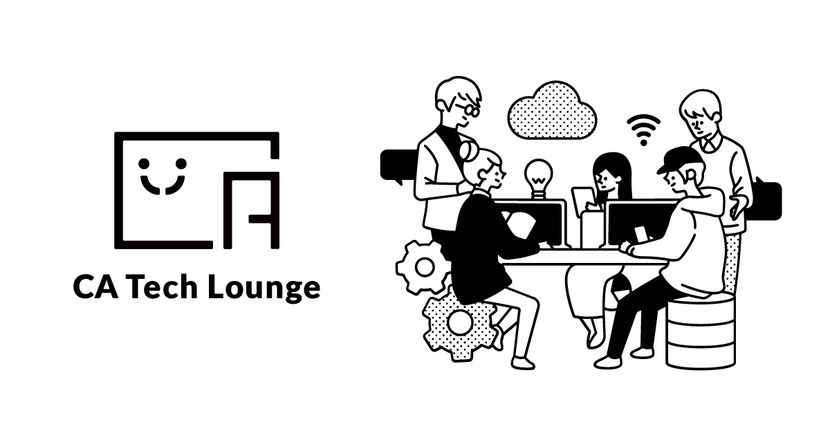メンターと歩んだ実務レベルへの成長—CA Tech Lounge卒業生の開発体験—

サイバーエージェントは、意欲あるエンジニア志望者向け学習コミュニティスペース「CA Tech Lounge」を運営しています。2025年には「CA Tech Lounge」の卒業生から5名が、サイバーエージェントに新卒入社しました。今回はそのうちの2名に、独学では越えられなかった壁をどう乗り越え、実務レベルへと到達したのか?「CA Tech Lounge」ならではの開発体験を振り返ってもらいました。
Profile
-

木村 颯馬
(株)WinTicket所属 バックエンドエンジニア
大学院卒業後、2025年新卒入社。「WINTICKET」における新機能の開発に携わっている -

福井 凜太朗
メディア統括本部DSC所属 データサイエンティスト
大学卒業後、2025年新卒入社。マッチングアプリ「タップル」の分析に携わっている。
「CA Tech Lounge」応募から合格へ
——異なる背景を持つ2人のチャレンジ
── お二人が「CA Tech Lounge」に入会することになった経緯から教えて下さい。
木村:在学中は数学を専攻しており、それまでコンピューターサイエンスには触れていませんでした。大学3年でプログラミングを独学で始め、大学院1年のときにはスタートアップ企業で開発インターンも経験しました。
もともと、サイバーエージェントの技術への取り組みやプロダクトに関心があり、2025年卒向けの夏季インターン説明会に参加した際に「CA Tech Lounge」2期生の募集を知り、応募を決めました。
福井:私はデータサイエンス学部で、動画メディアコンテンツに関する分析に取り組んでいました。学部2年の後半ごろから就職を意識するようになり、データサイエンスを、メディアや広告といった生活に身近な領域に活かせたらと思い、サイバーエージェントに興味を持ちました。
就職活動に向けて情報を集めていたとき、SNSで偶然「CA Tech Lounge」の募集を開始したことを知り、「これは挑戦してみたい」と思い、すぐに参加を決意しました。
── 「CA Tech Lounge」参加にあたっては選考があります。どのようなプロセスで入会に至ったのでしょうか?
福井:まず書類選考があり、その後、機械学習・データサイエンス、バックエンドといった分野ごとに課題が用意されていました。用意された課題に取り組むか、自分の過去の制作物を提出するかを選べるのが特徴的でした。
木村:私は、自分で開発したWebアプリを提出する形を選びました。旅行のときに使える、キャンプ場や温泉をマッピングするWebアプリで、フロントからバックエンドまで一人で作り込んだものです。それを提出し、面接を経て参加が決まりました。福井さんは課題の方でしたよね?
福井:はい。私が選んだのは、画像を分類する機械学習モデルを作り、それをAPIとして実装するという課題でした。5つほどの選択肢の中から、自分の強みを発揮できるものを選び、全力で取り組みました。面接後に合格の連絡をいただいたときは、本当に嬉しかったです。
木村:私も、合格の知らせをもらったときは素直に嬉しかったです。技術的な内容を、現役エンジニアの方がフラットな視点で見てくれて、しっかり評価してもらえるという経験は、なかなか得られないものだと思います。

成長の再現性を支える、体系的な学習プロセス
── 毎シーズン40名近くが参加されていますが、どのようなメンバーが集まっているのでしょうか?
福井:年齢層もバックグラウンドも多種多様です。高校生でアプリ開発をしている人や、論文を書いている社会人の方もいるので、さまざまな視点からの学びがあり、自然と視野が広がりました。
木村:参加メンバーの多様性に加えて、メンターの存在も大きかったです。目標設定から日々の進捗管理まで、ずっと伴走してくれるのが心強かったですね。
福井:メンターのサポートを受けていて実感したのは「エンジニアとして成長するには、技術力だけでなく、考え方や目標設定の仕方も重要」という点です。
「CA Tech Lounge」ではまず、自分が将来どうなりたいかを言語化して、それに必要なスキルや知識を明確にします。そしてメンターと一緒に学習計画を立て、2週間ごとに振り返りを重ねていく。短いスパンでの対話が、学びを加速させてくれました。
木村:私は「サイバーエージェントで活躍できるバックエンドエンジニアになる」というゴールを設定しました。
サイバーエージェントではGoが使われるプロダクトが多かったので、まずはGoでAPIサーバーを作るところから始めて、CI/CDやDockerなど、実務で必要な技術も段階的に学習しました。
あとは「ABEMA」のメンターの方から実際の技術スタックや、チームでの開発における実務的なコードの書き方を学ぶことができたのも大きかったです。
学生時代に参加したスタートアップでのインターンでも多くの学びはありましたが、「CA Tech Lounge」ではさらに、大規模なプロダクト開発に必要なCI/CDや運用設計など、より実務に近い技術や考え方を体系的に身につけることができました。
独学や個人開発では越えられなかった壁を超えられたのは、まさに「CA Tech Lounge」のおかげです。サイバーエージェントの技術水準の高さにも直に触れられて、大きな刺激になりました。

就職活動の支えに
——CA Tech Loungeの伴走力
── 就職活動で「CA Tech Lounge」をどのように活用されましたか?
福井:私の就職活動は少し長期戦で、3月の本選考では一度不合格になったんですが、「再チャレンジ制度」を利用して、9月にもう一度面接を受け、10月に内定をいただきました。
木村:そこからの巻き返し、すごいですね。なにか合格の決め手になった変化はありましたか?
福井:正直、技術面で劇的に成長したわけではないと思います。それ以上に、「会社や仕事への理解」が深まったことが大きかったです。
自分がどう働きたいかだけでなく、会社がどんな人を求めているのか、どう貢献できるのかを言語化できるようになったんです。技術力だけではなく、「この人ならきっと活躍できそう」と思ってもらえることの大切さを実感しました。
木村:たしかに。「うちのチームに来たら、こんなふうに活躍してくれそうだな」って思ってもらえるのって、すごく重要ですよね。まだ実績が少ない分、技術力だけで信頼を得るのはやっぱり難しい。
福井:だからこそ、自分の目指す方向性や価値観を、きちんと言葉で伝えることがすごく大事だと思うようになりました。
「CA Tech Lounge」では、メンターさんとの対話の中で「自分は何が得意で、どんな場で力を発揮したいのか」を整理する機会が多かったので、それが就職活動にも活きたと思います。
自分を売り込むというよりも、「自分はこういうデータサイエンティストで、会社に入ったらこんなことを実現したいです!」と自然に伝えられる状態になれたことが、結果的に信頼につながったのかなと感じています。
── 就職活動を通して「CA Tech Lounge」で一番良かったことは何でしたか?
福井:メンターさんに継続して伴走してもらえたことです。就職活動が長引いたときには、正直メンタル的に苦しい時期もありました。でも、進捗を見守りながらサポートしてくれる存在がいたことで、「一人じゃない」と思えたのが大きかったです。
木村:それは私もすごく感じました。私の場合、大学では数学専攻で、IT分野に進む仲間が身近にいませんでした。就職活動でも孤独を感じることが多かったですが、「CA Tech Lounge」では、メンターさんという自分の挑戦を見続けてくれる人がいたことで、心が折れそうな時にも前を向くことができました。
福井:他にも、さまざまな事業部の社員の方と直接話す機会があり、職種や働き方に対する理解がとても深まりました。2年間「CA Tech Lounge」に参加していたことで、会社の雰囲気もよく知ることができ、入社後のギャップもほとんどありませんでした。

── 実際に入社されてみて、「CA Tech Lounge」での経験がどのように活きていると感じますか?
木村:入社してみて驚いたのは、2年目でサービス全体に関わる機能を担当する人や、3年目で新規事業を立ち上げている人がいるなど、若手に大きな裁量が与えられていることでした。
「CA Tech Lounge」での学びがあったおかげで、技術スタックにも戸惑うことなく、配属後2日目にはAPIのプルリクエストを提出できました。実務レベルのコードを書くトレーニングが積めていたことが、現場での立ち上がりの速さにつながったと思います。
福井:私はもともとメディアサービスに興味がありました。ただ、外部からの分析では制約が多かったこともあり、自分の手でプラットフォームのデータを扱える環境で働きたいと考えて、Data Science Center (DSC)を志望しました。
現在はマッチングアプリ「タップル」のレコメンドチームに所属し、分析や効果検証を担当しています。日々の業務では、「この分析は事業にどんなインパクトを与えるのか?」という視点が常に求められます。
大学の研究ではこうした視点を持つことは難しかったと思いますが、「CA Tech Lounge」で社員の方と何度も話す中で、ビジネスへの意識が自然と身についたことが、今の仕事にも確実に活きていると感じます。

── 最後に、これから「CA Tech Lounge」に参加しようか迷っている学生に、メッセージをお願いします。
福井:狭いコミュニティにいると視野がどうしても狭くなりがちですが、「CA Tech Lounge」には、年齢も専門分野も異なる人がたくさん集まっていて、日常では出会えないような刺激的な会話や発見にあふれています。
今は技術的にハイレベルな参加者が増えてきていますが、だからといって現時点での技術力に自信がなくても大丈夫です。「今の自分を変えたい」「もっと成長したい」という気持ちがあれば、仲間と一緒に成長できる環境があります。
木村:私も、独学だけではどうしても越えられなかった壁を、「CA Tech Lounge」で乗り越えることができました。
自分ひとりでは難しかったことも、メンターの支えや仲間とのやり取りがあったからこそ続けられたし、実務レベルにまで到達できたと感じています。
「本気で成長したい」と思っている方にとって「CA Tech Lounge」はとても良い成長機会が得られる場です。一人ではたどり着けない場所へ、仲間と、メンターと、一歩踏み出してみてください。
記事ランキング
-
1

『スキャンダルイブ』ヒットの裏側 ー「作る」と「届ける」を分断させないAB...
『スキャンダルイブ』ヒットの裏側 ー「作る」と「届ける」を分断させないABEMAの勝ち筋
『スキャンダルイブ』ヒットの裏側 ー「作る」と「届ける」を...
-
2

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...
社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代
社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...
-
3

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」
値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」
値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値...
-
4

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...
【対談】ML/DSにおける問題設定術
~ 不確実な業界で生き抜くために ~

機械学習やデータサイエンスがビジネスの現場で当たり前になりつつある今、求められているのは、ビジネスの課題を実装に落とし込み、運用し、継続的な価値を生み出す視点となりつつあります。
サイバーエージェントでは、こうした実践的なスキルを持つ次世代のデータサイエンティストを育成すべく、2025年11月、新卒向け特別プログラム「DSOps研修2025」を実施しました。
「技術を社会実装する際の『問題設定』こそが重要である」 この研修のコンセプトに深く賛同いただき、特別講師としてお迎えしたのが、半熟仮想(株) 共同創業者であり、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」にも選出された齋藤優太氏です。
第1部では、半熟仮想(株) 共同創業者であり、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出された齋藤優太氏をお招きし、「ML/DSにおける問題設定術」について講演いただきました。 続く第2部では、齋藤氏に加え、当社執行役員兼主席エンジニアの木村、AI Lab リサーチサイエンティストの暮石が登壇。「現場視点×経営視点」でパネルディスカッションを実施しました。
本記事では、白熱した第2部「パネルディスカッション」の模様をダイジェストでお届けします。