Difyで変わるサイバーエージェントの働き方 ~「5分でできる」から始める生成AI普及戦略

生成AIの可能性が広がる中、多くの企業がその活用に注目しています。その一方、実際の現場では「どこから始めればよいか」「限られた時間でどう取り組むか」といった課題に直面することも少なくありません。
AIオペレーション室で生成AIを用いた業務効率化およびエヴァンジェリストを務める李俊浩は、「5分でできる簡単な使い方」から始める啓蒙活動を通じて、社内のDify活用を右肩上がりで普及させています。継続率を高める「楽しく広める」戦略から、生成AI時代の新しい働き方を支える実践的な取り組みに迫ります。
Profile
-

李 俊浩(AIオペレーション室 ソフトウェアエンジニア)
全社的なAI活用戦略を推進するテクノロジーリーダー。生成AI活用コンサルティングの第一人者として、数々のプロジェクトを成功に導く。Dify Community Meetup (JP)の運営を通じて、日本のAIコミュニティの発展にも貢献している。
「5分だけ試してみる」で変わる社内の生成AI活用マインド
── 李さんのエンジニアとしてのバックグラウンドを教えて下さい。
2013年にサイバーエージェントのゲーム子会社にバックエンドエンジニアとして入社しました。その後、サイバーエージェント本社での大規模開発を経て、現在はAIオペレーション室で生成AIを用いた業務効率化および、Difyのエヴァンジェリストとして活動しています。
── 多岐にわたる事業ドメインの中に生成AIを導入する際、どんな課題があると実感していますか?
2024年頃に、AIオペレーション室で実施した社内アンケートの結果、多くの方が生成AIの学習は受けているものの、実際の業務でのAIツールの活用方法に悩んでいる点が浮かび上がりました。その理由として、日々刷新される新しい生成AIツールのキャッチアップだけでも大変なことや、足元の業務と並行しながら新しい生成AIツールを試す時間を確保するのが難しいこと等が挙げられました。
そこで、忙しい方でも取り組みやすいように「5分でできる簡単な活用例」などのカジュアルな啓蒙活動を開始しました。例えば、AIアプリケーションを開発・運用できるローコードプラットフォームであるDifyを使えば、プログラミングの知識がなくても、プロンプトを言語化するだけで業務効率化ができるようになります。
Dify勉強会の事例では、広報やIRチームの記事作成のフローそのものを変え業務効率化に大きく貢献する事例も生まれています。
社外向けには「Dify Meetup Tokyo」を主催し、非エンジニアの業務効率化の生産性向上をテーマに毎回200~500名規模の参加者に向けて登壇。並行して社内でも30回以上の勉強会を実施した結果、特に非エンジニア職のDify利用が急拡大しました。
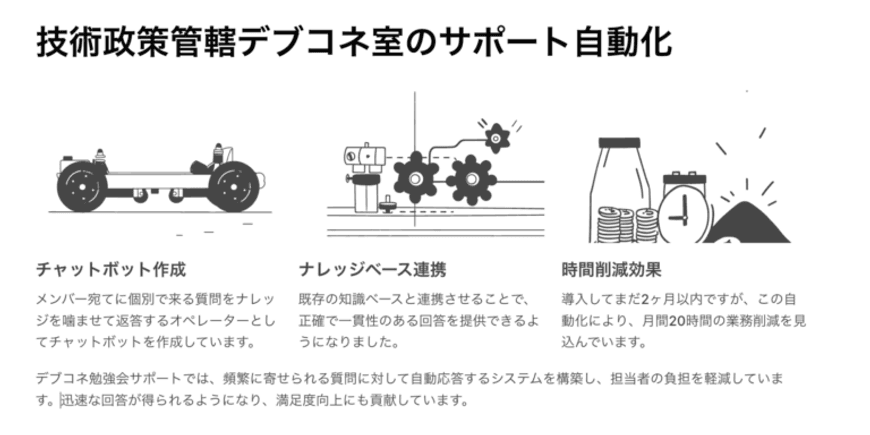

「戦略を練る時間」を生み出すDify活用の実際
── 具体的にどんな業務がDifyで効率化されているのでしょうか?
AIオペ室が実施したインタビュー後に、個別のヒアリングを重ねてみると「日々の作業の中で、定型的なオペレーション業務に時間を取られて、本来やりたかった業務に集中できていない」という課題も発見できました。
従来は、エンジニアの稼働をかけて開発していた業務アプリケーション開発ですが、Difyはノーコードで業務アプリケーションを誰でも開発できるのがポイントです。スプレッドシート連携やSlack連携といった用途であれば、Difyで十分対応できます。実際に既存の社内ツールの多くをDifyに置き換えることも可能です。
定型的なオペレーション業務が削減され、日々の業務の効率化ができた結果、マーケティングや競合比較をした上で戦略を練ったり、キャンペーンを考えたりといった、より価値のあるコアの仕事に専念できるようになったようです。
例えば、ある部署では、これまで1時間かかっていた議事録作成がDifyによってわずか15分に短縮されました。これが積み重なり、部署全体で月に15時間もの工数削減につながっています。チーム単位では月に20時間、日数にして2.5営業日分もの時間を創出した事例も報告されています。
── Difyを選定する際に他の競合製品も検討されたのでしょうか?
LangChainやLangGraphなど様々なツールを検討しました。MicrosoftやAWSのBedrockなども候補でしたが、ビジネス職の利用を想定して、UIの分かりやすさやアカウント発行の手軽さなどを総合的に判断し、Difyが最も適していると判断しました。
── 運用面ではどのような工夫をされているのでしょうか?
Difyはオープンソースなので、気軽に活用できる点が大きな決め手でした。まずAIオペレーション室内でセルフホスティングして価値検証を行い、効果を確認してから全社に普及させました。
当初は大人数での利用を想定していなかったため、ユーザーが急増した際には負荷分散や同時接続の改善などを行いました。特に社内ドキュメントを参照する機能では、高精度のベクトルデータベースを導入するなど、安定運用のための改善を続けています。
── エヴァンジェリストの活動として、社外の反響はいかがでしょうか?
社外向けでは、Dify Community (JP)およびDify Meetup Tokyoという非エンジニアの業務効率化の生産性向上をテーマに毎回200~500名規模のコミュニティ運営をしています。他にも、社内向けにDify勉強会を開催したり、「CA.ai」というサイバーエージェントのAI活用事例でAIエージェントなどAIに関する技術的な発表をしたりしました。また、エンジニア向けにはCursorやClaude Codeなど最新のAI開発ツールの活用方法など啓蒙活動もしています。
最近の活動としましては、エンジニアの生産性向上をテーマに情報発信を行っています。
直近では、社内で「WINTICKET Claude Code勉強会」を開催したほか、社外イベントで1500人規模のAIエージェントイベントや850名規模のAI開発ツールのイベントにも登壇しました。
これらの場では、適切なAIエージェントの活用やAI開発ツールの選定が、開発の生産性向上に直結する点を強調してお伝えしました。
質疑応答や懇親会でよくいただく質問で多いのは「どうやってAIツールを社内に普及させたのか?」です。
普及のポイントは「楽しく広める」ことです。生成AIをなかなか使いこなせていない人のために「5分でできる議事録要約」「5分でデータ分析」など具体的で簡単な例から始めています。プロンプト入力するだけで、音声アップロードや記事テキスト入力でAIが結果を出してくれるという体験をしてもらいます。

「生成AI時代を成長の機会」と捉える視点
── 李さん自身のエンジニアとしてのビジョンをお聞かせください。
エンジニアリングの考え方に大きなゲームチェンジが起きていますよね。生成AIを活用してどこまで開発生産性が上がるのか。AIオペ室でも日々、仮説と価値検証を行っています。
私自身も、開発生産性の向上を目指して、様々なアプローチを検討しています。AIが自動で行うパターンと、エンジニアが手動でコードを書くのを効率化するパターン、完全にAIに代替して自動化するパターンに分けて考えています。
手動の場合はClaude CodeやCursorなどを使い、重要な部分は人が見ています。完全にAIにやらせる場合は、コード修正や検証をAIが行い、プルリクエストを出し、人がレビューしてマージ、テストしてリリースするという開発プロセス全体の自動化を進めています。
AIエージェントを活用することで、Issueを出すと自動でコードを書いてくれるケースも実用段階に入っていくと思われます。現在のAIエージェントではまだ精度の課題があり、多くの方は簡単なものだけAIにやらせて、複雑なロジックは対話しながら作業していますが、これも時間の問題かと思われます。
── 生成AIが開発現場に浸透していく時代において、これからエンジニアを目指す学生や若手の方へのアドバイスをお願いします。
エンジニアとしてのコーディング業務は変化していくと思いますが、私は脅威ではなく成長の機会ととらえています。重要なのは本質的な課題をとらえる思考力や問題を特定する能力を鍛えることです。
AIに正しく動いてもらうためには、正しく言語化して適切な指示を出す必要があります。「いい感じにやっといて」という曖昧な指示ではなく、「このプロセスが必要だからこれをやってください」と具体的に伝える力が求められます。そこで、従来からある分析手法のフレームワークやクリティカルシンキング、ペルソナを正しく設定できる人が、AIを上手に活用できています。
多くの人が積み重ねてきた知識は、時代が変わっても必要とされます。 成功パターンや正しいフレームワークをしっかり学んでおけば、時代が変わっても必ず活躍できます。コードを書くスキルに加えて、意思決定能力や正しい思考力を身につけることで、AIと協働する新しい時代のエンジニアとして成長していけるはずです。
技術の進歩は脅威ではなく、より創造的で価値のある仕事に集中できる機会です。若い皆さんにとって、これほどエキサイティングな時代はないのではないでしょうか。

オフィシャルブログを見る
記事ランキング
-
1

『スキャンダルイブ』ヒットの裏側 ー「作る」と「届ける」を分断させないAB...
『スキャンダルイブ』ヒットの裏側 ー「作る」と「届ける」を分断させないABEMAの勝ち筋
『スキャンダルイブ』ヒットの裏側 ー「作る」と「届ける」を...
-
2

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...
社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代
社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...
-
3

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」
値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」
値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値...
-
4

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...
【対談】ML/DSにおける問題設定術
~ 不確実な業界で生き抜くために ~

機械学習やデータサイエンスがビジネスの現場で当たり前になりつつある今、求められているのは、ビジネスの課題を実装に落とし込み、運用し、継続的な価値を生み出す視点となりつつあります。
サイバーエージェントでは、こうした実践的なスキルを持つ次世代のデータサイエンティストを育成すべく、2025年11月、新卒向け特別プログラム「DSOps研修2025」を実施しました。
「技術を社会実装する際の『問題設定』こそが重要である」 この研修のコンセプトに深く賛同いただき、特別講師としてお迎えしたのが、半熟仮想(株) 共同創業者であり、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」にも選出された齋藤優太氏です。
第1部では、半熟仮想(株) 共同創業者であり、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出された齋藤優太氏をお招きし、「ML/DSにおける問題設定術」について講演いただきました。 続く第2部では、齋藤氏に加え、当社執行役員兼主席エンジニアの木村、AI Lab リサーチサイエンティストの暮石が登壇。「現場視点×経営視点」でパネルディスカッションを実施しました。
本記事では、白熱した第2部「パネルディスカッション」の模様をダイジェストでお届けします。


