三菱UFJ銀行との協業から生まれた
「信頼でつなぐ広告 Bank Ads」
テクノロジーと倫理が交差する、広告DXの実践

2023年、三菱UFJ銀行とサイバーエージェントは、金融データと広告技術の融合による新たな広告事業「Bank Ads」を立ち上げました。
信頼性を前提とした広告のあり方が問われる時代において、銀行が保有する1st Party Dataと、広告業界で培われた開発・運用ノウハウを掛け合わせ、安心かつ効果的な広告体験の実現に挑んでいます。
本記事では、プロジェクトの中心メンバーである杉山・伊藤の両名が、「Bank Ads」の誕生背景や具体的な開発プロセス、信頼と成果の両立を目指すための思想や仕組み、そしてテクノロジーとビジネスの境界線を越えたキャリア観について語ります。
Profile
-

伊藤 寛武 (株式会社サイバーエージェント)
資産運用会社、コンサルティング会社、大学研究員を経て、2021年サイバーエージェントに入社。2023年9月より三菱UFJ銀行に出向(兼務)、データサイエンティスト・エンジニアとして、Bank Adsのグロースに向けた企画立案に従事。 -

杉山 侑吏 (株式会社サイバーエージェント 出向 株式会社三菱UFJ銀行)
大学研究員、ベンチャー企業での商品企画・データサイエンス業務の経験を経て、2023年にサイバーエージェントに入社。2023年9月より三菱UFJ銀行に出向(兼務)、データサイエンティスト・商品企画としてデータ分析や事業開発等の業務に従事。
三菱UFJ銀行 × サイバーエージェント、信頼と技術が融合した広告事業が始動
── まずは、おふたりのご経歴や現在の役割から伺えますか?
杉山:もともとはデータサイエンティストとしてキャリアを積んできましたが、最近は「事業開発をしています」と自己紹介することが多くなりました。サイバーエージェントにもデータサイエンティストとして入社しましたが、現在は三菱UFJ銀行様との協業プロジェクトに参画し、データサイエンティスト・事業開発担当として動いています。
データサイエンティストのバックグラウンドも活かし、「どうすればデータや技術を実際の事業価値に転換できるか」を常に考えている感覚です。
伊藤:私はもともと、広告プロダクトのデータサイエンティストとして開発に携わっていました。ちょうどAppleがAppTrackingTransparency(ATT)を導入し、広告業界全体が大きな転換点を迎えていた時期でした。ユーザーの個人情報に関する意識の変化を開発現場でも感じる中で、「技術」だけでなく「広告という仕組み」そのものに関心が広がっていきました。
現在はデータサイエンティストとして、プロダクトやシステム開発の推進を担っています。いわば、開発責任者のような立場です。
── サイバーエージェントが金融機関と協業というのは、少し意外な印象もあるのですが、どのような背景でスタートしたのでしょうか?
杉山:このプロジェクトは、三菱UFJ銀行様と私たちサイバーエージェント、双方の事情が重なったタイミングで立ち上がったと理解しています。
■ デジタル広告事業「Bank Ads」の設立と取り組み 金融データ×デジタル広告で創出する新しい価値
三菱UFJ銀行様の背景については、あくまで外部の立場からの見立てになりますが、2021年に銀行法が改正されたことが一つの大きな転機だったのではないでしょうか。長期にわたる低金利の影響もあり、「これまで築いてきた口座基盤を、どう収益化するか」がメガバンク共通の課題となっていた時期だったと思います。
そうした中で、口座保有者との信頼関係を前提に、新たなビジネスの可能性を模索する流れがあり、その選択肢のひとつとして「広告」が検討されたのではと推測しています。もちろん、インターネット広告は三菱UFJ銀行様にとって本業ではありません。だからこそ、長年この分野に携わってきたサイバーエージェントとの協業に、可能性を見出していただけたのではないか──そんなふうに理解しています。
伊藤:当時、インターネット広告業界全体も大きな転換点を迎えていました。3rd Party Cookieの段階的廃止やAppleのATTの導入など、ユーザーの個人情報や行動履歴に関する取り扱いルールが、大きく変わろうとしていた時期です。
背景には、「知らないうちに自分のデータが使われている」ことへのユーザーの違和感や懸念があり、広告業界としても、これまでの“効率重視”のアプローチを見直す必要が出てきました。
サイバーエージェントでもこの流れを受けて、プライバシーラボという専門組織を立ち上げ、Privacy Sandboxの検証など、広告の未来を見据えた取り組みを進めていました。
■ プライバシー保護で変わるネット広告 プライバシーラボが描く健全な広告エコシステムを目指して
そうした中でサイバーエージェントとして注目していたのが、業務を通じて収集された1st Party Dataを起点にユーザーに最適化された広告を配信することでした。
── プロジェクトが動き始めた初期段階では、どんなことから取り組み始めたのですか?
伊藤:プロジェクト初期は、いきなり巨大なアプリケーションの構築を開発するところから始めるのではなく、「できるところから一歩ずつ」のアプローチでした。たとえば、私たちが銀行内のデータウェアハウスにSQLでクエリを投げ、広告配信候補のセグメントを作成するところからスタートする等です。
システム連携が難しい環境下でも、銀行内で完結するアーキテクチャを構築しながら、まずは小さな検証から広告効果を確かめ、段階的にスケールさせていった、という流れです。
この点、実際に銀行内に出向している杉山さんは、どう感じていますか?お客様に近いところにいる視点から見る「Bank Ads」の価値や可能性を聞いてみたいですね。
杉山:「Bank Ads」には、単なるデータ活用という枠を超えた大きな可能性を感じています。
まず、私自身はデータサイエンティストでありながら多くの時間を広告主のお客様と直接商談させていただくことに時間を使っています。
お客様と接する中で私たち自身が勉強させていただくことは非常に多く、そうした声をもとに「プロダクトの提供価値」を考えて、三菱UFJ銀行様も含めた「Bank Adsチーム」全体の中で議論をしています。
ともすると、私たちデータサイエンティストは「データをどう活用するか」といった技術的な視点に意識が向きがちですが、実際にお客様と会話する中でより大きな視点に立ってプロダクトの価値を考えさせられる場面が多くあります。
例えば、「ブランドセーフティ」もその一つです。「信頼できる媒体で自社の広告を配信できること」に価値を感じてくださるお客様は多く、「信頼できる文脈で広告を届ける」とはどういうことかを、改めて考えるようになりました。
■「Bank Ads」で出稿されたお客様の声
また、信頼できる媒体を作るということは三菱UFJ銀行の口座保有者の方のユーザー体験をきちんと設計するということでもあります。
銀行に出向していることで「三菱UFJ銀行のお客様目線で違和感がないか」という視点もより強くなりました。
行内の方々がさらなる顧客体験の改善を目指して日々お仕事をされている姿に触れ、広告ビジネスも口座保有者の方にとってより有益な情報提供となるよう、日々勉強させていただきながら取り組んでいます。
そうした背景から「Bank Ads」では、「ブランドセーフティ」を前提に広告体験を設計しています。
例えば、三菱UFJダイレクトアプリ内の広告は、CTRで0.8~1.2%という高い成果が出ています。ユーザーが安心できる環境だからこそ、自然に反応が生まれている。それが今の手応えです。
また、「データをどのように使うか」もブランドセーフティを前提とした広告設計において重要になります。ユーザーが「知らないうちに自分のデータが使われること」に違和感を持つのは自然な感覚で、そこにどう向き合っていくかは、これからの広告にとって重要なテーマだと感じています。つまり「ブランドセーフティ」の考え方は、GDPR(※1)やATTが掲げる理念とも重なる部分があります。
広告をどう最適化するかだけでなく、「どう信頼されるか」を技術の力で実現していく。それが「Bank Ads」が目指している方向性です。
(※1) 「GDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)」。EU域内の個人データ保護を規定する法として、2016年4月に制定、2018年5月25日に施行。GDPRは個人データやプライバシーの保護に関して、EUデータ保護指令より厳格に規定する。また、EUデータ保護指令がEU加盟国による法制化を要するのに対し、GDPRはEU加盟国に同一に直接効力を持つ。
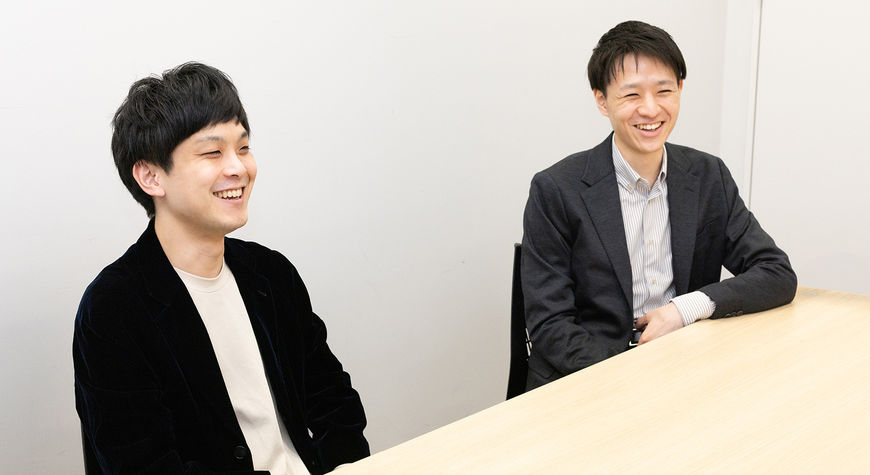
1st Party Dataだからこそ、誠実な設計が問われる
── 3rd Party Cookieに課題感が集まる中、ともすると「1st Party Dataだから安心」みたいな感覚にもなりがちですが、本当に安心と言えるのでしょうか?
伊藤:1st Party Dataだからといって、無条件に安心というわけではありません。
透明性も高いと言われていますが、「同意さえ取れていれば問題ない」という発想は危ういと感じています。
杉山:こうした「見えにくい同意」の問題は、広告主様からもよく問われます。特に銀行という、個人の金融資産に関わるセンシティブな情報を扱う場では「安心・安全なデータ活用」が強く求められます。三菱UFJ銀行様でも、データの使用にあたって事前の同意取得と目的の明示を徹底し、利用者が納得できる形で運用するという姿勢を持っていて、そこから学ぶことも多くありました。
伊藤:こういった背景があるからこそ「Bank Ads」では「気持ちよく見ていられる広告体験」を目指しています。これはアドテクノロジーやUI/UXといった単なる技術の問題だけではなく、媒体としての誠実さや倫理観が問われる領域です。簡単なことではありませんが、「信頼される広告媒体をゼロからつくる」という挑戦には、それだけの価値があると感じています。
杉山:データがあるからといって、すべてを活用すべきとは限りません。「ターゲティングできるからやる」のではなく、「それは本当にユーザーのためになっているのか」を一度立ち止まって考える。そうした姿勢や倫理観が、これからの広告媒体には不可欠だと思います。
── お二人自身、プロジェクトを通して考え方や意識に変化はありましたか?
伊藤:ありますね。以前は、「1st Party Dataがあれば、精度の高い広告が打てる」という前提で動いていました。でも実際には、それだけでは広告主に響かない。
「それって口座保有者や広告主にとって本当に良い体験なんだっけ?」という視点を、何度も突きつけられました。そこから「広告って誰のためにあるのか」を考えるようになったのは、大きな変化です。
特に、金融データのようなセンシティブな情報を扱う以上、広告の最適化以上に「口座保有者にどう受け止められるか?」を意識した設計が必要だと実感しています。
杉山:同感です。私も、広告って「届け方」だけじゃなく「届けるための文脈」まで含めて設計すべきだと強く感じるようになりました。たとえば銀行のサービス画面に広告を出すときにも、見せ方や内容がふさわしいかどうか、細かく配慮する必要があります。
三菱UFJダイレクトアプリのように信頼を前提とした場所で広告を届けるには、細部の設計まで責任を持たなければいけないと感じています。
── 協業だからこその難しさや、課題に感じていることはありますか?
杉山:「Bank Ads」では、いつも「ロマンとそろばん」の両立を意識しています。
たとえば「銀行が広告プラットフォームになる」という構想は非常にユニークで、ブランドセーフティを軸に、新しい広告のかたちを社会に提案できる。これは「ロマン」だと思っています。
一方で、広告配信は事業です。実利的な成果が出なければビジネスとして存続できません。現場では「CTRをもっと上げたい」「もっと柔軟な表現にしたい」といった、広告主からの率直な要望も日々届きます。こうした「そろばん」の視点、つまり短期的な広告効果をどう確保するかも、避けては通れません。
広告ビジネスでは「toC=受け手の個人のお客様」と「toB=広告主/出稿側」の両方と向き合う立場にあります。どちらか一方に偏れば、もう片方の期待を満たせなくなってしまう。特に「Bank Ads」では、先ほどの通り、三菱UFJ銀行の個人のお客様からの信頼・信用が媒体としての大きな価値の一つになっています。
だから私たちは、これまで以上に、両方の間で「どんな運用や表現なら両立できるか」を設計し、具体的な調整案として提示することを心がけています。
理想を追いすぎても現実から乖離するし、目先の数字やKPIばかり追えば、信頼という資産を失ってしまう。そのバランスを丁寧に設計していくことこそが、「事業会社のデータを活用した広告ビジネス」の面白さだと感じています。

技術とビジネスの境界線を越えて──協業DXで感じた新しいキャリア感
── お二人はエンジニアとしてのバックグラウンドを持ちながら、ビジネスサイドにかなり踏み込んだ動きをされていますよね。スタンス形成やキャリア観についても聞きたいです。
伊藤:私自身、エンジニアリングやデータサイエンスそのものにこだわりがあるというより、それらを使って「何を実現するか」に関心があるタイプです。
課題を見つけて、自分で提案資料を作って、杉山さんのように時には売り込むこともする。そういう動き方のほうが、結果的にビジネスも前に進むと感じています。
杉山:私も、職種にこだわるより「自分が価値を出せる場所」に軸を置いてキャリアを考えてきました。たとえば銀行の中に入ってプロジェクトを進める中で、自分の専門領域だけでは完結しない課題にたくさん直面するんです。
そうすると自然に「ここも自分が担おう」と思えるし、逆にそこに面白さもある。「いざとなったら自分で分析できる」という点も行動力の源泉かもしれません(笑)。
伊藤:サイバーエージェントはもともと、そういう越境的な動きを歓迎するカルチャーがありますよね。「エンジニアか、ビジネスか」という二択ではなく、その間に無数の立ち位置があるというグラデーション的な感覚。自分がどこに立つかを、自分でキャリアの色を決められる組織だと思っています。
── とはいっても、自分の専門分野から越境するのは勇気がいりますよね。時に不安もあると思います。
杉山:私自身、NPOの立ち上げに取り組んだり大学で研究したりした後、スタートアップにてデータサイエンティストのキャリアを始めて、今は事業づくりにも関わっています。でも、明確なロールモデルがあったわけじゃなくて、「今、自分が価値を出せるのはどこか」を都度判断してきた結果、今の役割があると思ってます。
たしかにキャリアの初期には、ある程度の「ロールモデル的な正解」が用意されていると安心するのはわかります。でも、ある年次やステージから、その道は自然と消えていく。そんな時、キャリアのロールモデルや誰かの背中をなぞるのではなく、自分の意思で道を切り開けるか。そこにテクノロジー×ビジネスならではの面白さも、難しさもあると思っています。
伊藤:まさにその感覚ですね。あえて「自分の立ち位置を職種で決めない」ことが大事かなと思ってます。目的を定めて、そのために必要なスキルや領域にどんどん踏み込んでいけるかどうか。キャリアって、ベストプラクティスに合わせるものじゃなくて、自分にあうようにカスタマイズすることなんだと思います。
たとえば、私たちの好きな漫画『ONE PIECE』(集英社)で言えば、グランドライン(偉大なる航路)に入った後の世界に似ています。一見、誰もが同じゴールを目指しているようで、それぞれが違う航路を選び、自分なりの理由で航海を続けている。キャリアもまさにそうで、正解の地図は存在しない。
特にテクノロジー×ビジネスのDX領域は、まだ正解もなければ事例も少ない「新世界」のような事業ドメインです。エンジニアが事業ドメインに越境できるベストな環境だと思っています。
杉山:テクノロジー×ビジネスのDX領域は、実はすごく自由なことでもあって。正解はないけど選んだ道を最適解にしていくことはできる。テクノロジーでそれを実現するために、若手に裁量権があるのがサイバーエージェントの良さでもあります。そういった企業カルチャーがあるからこそ、我々が「Bank Ads」という新しいチャレンジに本気で取り組めている理由でもあると思います。
オフィシャルブログを見る
記事ランキング
-
1

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像
サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像
サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像
-
2

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...
社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代
社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...
-
3

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ
Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ
Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ
-
4

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...
【対談】ML/DSにおける問題設定術
~ 不確実な業界で生き抜くために ~

機械学習やデータサイエンスがビジネスの現場で当たり前になりつつある今、求められているのは、ビジネスの課題を実装に落とし込み、運用し、継続的な価値を生み出す視点となりつつあります。
サイバーエージェントでは、こうした実践的なスキルを持つ次世代のデータサイエンティストを育成すべく、2025年11月、新卒向け特別プログラム「DSOps研修2025」を実施しました。
「技術を社会実装する際の『問題設定』こそが重要である」 この研修のコンセプトに深く賛同いただき、特別講師としてお迎えしたのが、半熟仮想(株) 共同創業者であり、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」にも選出された齋藤優太氏です。
第1部では、半熟仮想(株) 共同創業者であり、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出された齋藤優太氏をお招きし、「ML/DSにおける問題設定術」について講演いただきました。 続く第2部では、齋藤氏に加え、当社執行役員兼主席エンジニアの木村、AI Lab リサーチサイエンティストの暮石が登壇。「現場視点×経営視点」でパネルディスカッションを実施しました。
本記事では、白熱した第2部「パネルディスカッション」の模様をダイジェストでお届けします。


