対象者は1,000名以上、サイバーエージェントが日本一GitHub Copilotを活用している理由

当社ではAI時代においてもリーディングカンパニーであるために、技術力を駆使して会社の持続的な成長を創出することを目指しています。2006年より「技術のサイバーエージェント」ブランドを掲げていますが、それらを実現するため2023年を「生成AI徹底活用元年」とし、様々な取り組みを進めています(参照:「AI時代においてもリーディングカンパニーを目指す、サイバーエージェントの技術戦略」)。
AIによって、技術者を取り巻く環境は大きく変化しましたが、その最たる例がGitHubが提供するAIペアプログラマー「GitHub Copilot」ではないでしょうか。当社では2023年4月の全社導入以来、対象となる1,000名以上の技術者のうち約8割が開発業務に活用しており、アクティブユーザー数日本一、またGitHub Copilotへのコード送信行数、GitHub Copilotによって書かれたコード数も国内企業においてNo.1の実績です。
社内でGitHub Copilotの活用が大いに進んでいるのはなぜなのか、旗振り役を務めるDeveloper Productivity室 室長 小塚に話を聞きました。
Profile
攻めと守り、絶妙なバランス力が活用を後押し
── 導入開始から約8割のエンジニアが活用するに至るまで、どのような道のりを歩んできたのでしょうか?
社内でポリシーを整備するまでは各エンジニアが業務外で利用していたのですが、業務でも利用したいという声が多数出てきたため、2023年3月に一部プロダクトで試験運用を行いました。その結果を踏まえ、翌月には利用申請・請求フローを構築し、GitHub Copilot Businessの全社導入を開始しました。当社にはフェーズや規模の異なる様々なプロダクト・子会社がありますが、GitHub Copilotの活用は開発生産性向上において必要不可欠と考え、導入促進を促すために利用料金を全社で負担しています。また、同時に活用のための生成AIガイドラインを策定し発表しました。
その後、アーリーアダプターのエンジニアたちが活用方法に関する社内勉強会を開催したり、それら知見を社内報に掲載したことでさらに認知が広がり、利用者が増えてきました。加えて、API経由で利用者を把握できるようになったため、各事業部の利用状況を可視化する環境も整えました。
2023年8月にはGitHub社をお招きした社内勉強会を実施したほか、9月には「GitHub Copilotで変わる開発文化の現実」と題したイベントも開催しました(参照:「GitHub Copilotによる技術革新と未来のエンジニアリング」)。詳しくは、「1000人を超えるエンジニア組織へのGitHub Copilot利用促進している話」と題したブログ記事にまとめています。
また、2024年1月からはGitHub Copilot Enterpriseのクローズドベータに参加しました。実際の開発現場における活用事例や使ってみた感想についてもブログを執筆しましたので、ご興味のある方はぜひご覧ください。
── 全社導入にあたって、どのような点を工夫しましたか?具体的な取り組みを教えてください。
まず早々に着手したのは、利用状況を可視化できる環境の整備です。グループ全体の技術戦略を策定する横断組織「CTO統括室」のメンバーや各開発責任者がいち早く導入を促進したいという思いを持つ中で、対象者のうち誰がGitHub Copilotを有効化しただけに止まっているのか、もしくは積極的に活用しているのかが分からず、利用を促進しにくいという声が多かったからです。
また、実態を把握できるよう導入すべき人と導入しなくても良い人を区別しました。例えばドキュメント閲覧のためにGitHubアカウントを持っている企画職やbotアカウント等を除外することで、各事業部の正しい利用状況を理解した上で導入推進を行えるようにしました。
それらに加えて重要なのが、導入促進が “魔女狩り” のようになってはいけないということです。例えば利用者を増やすために、SlackのDMなどで名指しで利用を促す方法も考えられると思いますが、負荷になる可能性があるので実施していません。未利用の人たちには、定期的なアンケートを通し、上長許可や利用方法が分からない等導入の障壁となるものがないか、ヒアリングしています。
── アクティブユーザー数だけでなく、GitHub Copilotへのコード送信行数、GitHub Copilotによって書かれたコード数が国内企業においてNo.1とのことです。サイバーエージェントがこれらを実現できた理由は何だと思いますか?
当社独自の日本語LLM開発や「生成AI徹底理解リスキリング」など、新しいことに積極的に挑戦する社風が根付いているからだと思います。また、ボトムアップで現場エンジニアの要望を受け止めながらも、会社として抑えておく部分はしっかりと守るサイバーエージェントのセキュリティチームの絶妙なバランス力が、これほどスピード感のある導入・活用に繋がったのではないでしょうか(参照:「『免疫』のようなセキュリティチームを作りたい~主席エンジニアたちが向き合う情報セキュリティ対策~」)。
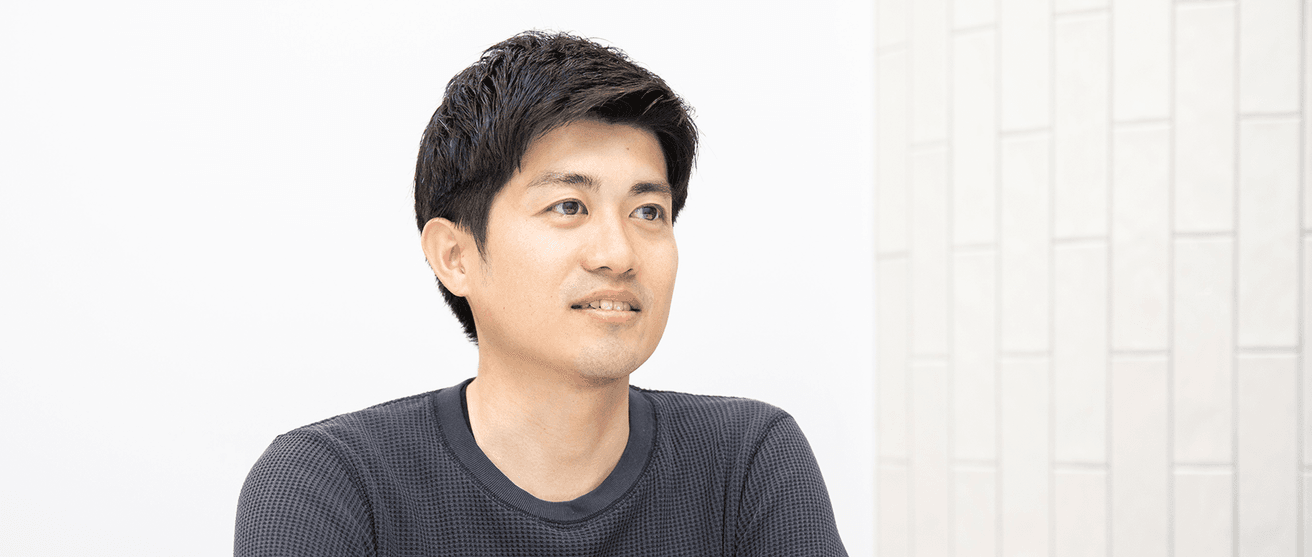
今後エンジニアに求められるスキルとは?
── GitHub Copilotの活用は、開発生産性向上のどのような点に寄与したと考えていますか?
先日実施したアンケートによると、エンジニアの約半数がコーディング業務を1-2割削減できたと回答しています。加えて約4割のエンジニアからは2割以上削減できたという結果が出ており、その分次の施策設計を行うなど、本来人間が労力を使うべきクリエイティブな領域に時間を割くことができていると考えています。
また、コーディング業務の効率化に伴い、色々な施策をスピーディに打てるようになったという点でも寄与していると思います。ユーザーの反応を見ながら次々と施策を実施できるようになったことで、プロダクトの改善スピードは今後さらに速くなっていくでしょう。
さらに、GitHub Copilotのメリットは学習効率も大幅に向上することです。私自身、日常的に書かない言語でコーディングする際、より恩恵を受けていると感じます。チャット機能を使えば、よく分からないコードをブラウザで検索せずともその場で教えてくれますし、エラーの解決方法も瞬時に分かるようになりました。
今後他のツールも活用しながら、コーディングだけでなくリリース作業やレビュー、運用面においても生産性向上に関する取り組みを積極的に推進することで、1年後には20%から30%、3年後には50%を目途にさらなる効率化を目指しています。
── コードを書く時間が大幅に減り、新しい言語への学習コストも下がるとなると、今後エンジニアに求められるスキルは大きく変わっていくのでしょうか?
エンジニアに求められる本質的なスキルは変わらないと考えています。生成AIを取り巻く環境の変化は驚くほど早いですが、新たなツールを使いこなすには、これまでもエンジニアに必要とされていた好奇心や日々真摯に学ぶ姿勢がより一層欠かせません。開発生産性を向上させられるツールも数多く出ているので、そのような領域にもきちんとアンテナをたててキャッチアップし、チームや会社にインパクトを与えられるようなエンジニアがより必要とされるのではないでしょうか。
また、コードを書く時の細々とした知識はAIが補完してくれますが、何らかの課題を解決するためにそれらを咀嚼しシステムに落としこむ設計力や、限られた制約の中で決断し実行する力は、人間にしか培えないものだと思います。
── 最後に今後の目標を教えてください。
サイバーエージェントグループのエンジニア全員がGitHub Copilotを活用できる状態を目指したいです。今年中に、コーディングのほぼ全てを自動化するGitHub Copilot Workspaceがリリースされると発表されました。開発生産性が飛躍的に向上し、エンジニアにとって非常にインパクトの強い機能です。その下地作りとしてエンジニア全員がGitHub Copilotを活用している状態を構築しておけば、GitHub Copilot Workspaceを活用した大きな事業貢献を実現できると考えています。

オフィシャルブログを見る
記事ランキング
-
1

生成AIが広告運用を再構築。2.4万時間削減目指す「シーエーアシスタント」とは
生成AIが広告運用を再構築。2.4万時間削減目指す「シーエーアシスタント」とは
生成AIが広告運用を再構築。2.4万時間削減目指す「シーエ...
-
2

サイバーエージェントの“自走する”人材育成 ー挑戦する企業文化ー
サイバーエージェントの“自走する”人材育成 ー挑戦する企業文化ー
サイバーエージェントの“自走する”人材育成 ー挑戦する企業...
-
3

コンテンツ愛が受け継がれる未来へ。ニトロプラスとサイバーエージェントの新た...
コンテンツ愛が受け継がれる未来へ。ニトロプラスとサイバーエージェントの新たな挑戦
コンテンツ愛が受け継がれる未来へ。ニトロプラスとサイバーエ...
-
4

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...
女性エンジニアのための技術とキャリアのカンファレンス 「Women Tech Terrace 2024」開催レポート

昨年に引き続き、2024年6月22日(土)に女性エンジニアのための技術とキャリアのカンファレンス「Women Tech Terrace 2024」を開催いたしました。今年で4回目となる当カンファレンスでは、「女性エンジニアが "長く自分らしく" 働くことを応援する」をコンセプトに、キャリアに関するパネルディスカッションや、技術に関する様々なセッションをお届けしました。
こちらの記事では写真とともに、当日の様子をお伝えします。



