【クリエイター対談】次の10年へとつづく、「Ameba」のリブランディング

2004年に「アメーバブログ」としてスタートした「Ameba」。2024年9月に20周年を迎え、ブログサービスを超えたメディアプラットフォームとして次の10年へとつづくブランドとなるべくリブランディングを実施。
また、新たなブランドコンセプト「つくる、つむぐ、つづく、Ameba LIFE」を制定しました。
本記事では、20周年プロジェクトを担当したアートディレクターの原とクリエイティブディレクターの武本が、リブランディングに至るまでの様々なプロセスや想いを振り返ります。
Profile
-

原 佑一 / AmebaLIFE事業本部 Ameba Brand Center
東京都立大学 システムデザイン学部 インダストリアルアート学科卒業後、2021年サイバーエージェントに新卒入社し、AmebaLIFE事業本部に配属。UX改善や新機能開発のUIデザインを担当。現在はAmebaLIFE事業本部のアートディレクターとして、キービジュアルやブランドサイト、ブランドムービーなど、自らも手を動かしながら制作している。 -

武本 敏治 / AmebaLIFE事業本部 Ameba Brand Center
2012年にサイバーエージェントに中途入社以来、メディアサービスの新規立ち上げやリニューアルを複数担当。現在はAmebaLIFE事業本部のクリエイティブディレクターとして、「Ameba」および周辺事業のブランド戦略、デザイン戦略を担当。
「Ameba」の不変的な価値を再定義
武本:「Ameba」のリブランディングの起点は、組織の存在意義の見直しから始まりました。ブログサービスとしてのビジョン・ミッション・スローガンなどはつくってきましたが、「Amebaが持っているものを各サービスに活かしきれていない」という感覚がチーム内にあったからです。「ブログサービスを超えたAmeba」へ大きく印象を変える必要があるという経営判断で、社内各所に相談しながらリブランディングを進めることにしました。
原:コピーライティングで広告事業の社員に協力してもらったり、動画制作で「ABEMA」の映像クリエイターに協力してもらったり、他部署のクリエイターとの掛け合わせでモノづくりができるのが、多方面に事業を展開しているサイバーエージェントならではで、チームで創ることができる面白さだなと思いました。そうやってブログ以外のサービスも含めた新しい伝え方をみんなで考えた先に、「Amebaが今までやってきた事業の共通項は生活・人生である」という認識で、Amebaの新たなブランディングとして合致していったんですよね。
武本:そうなんです。だからこそ「生活に根ざしたコンテンツを提供する」「ユーザーの人生を変えるような体験を生み出す」といった「Ameba」の不変的な価値をより強く示した言葉に仕上げました。元々あったビジョン・ミッションだけでは“言葉の強度が足りていない”実感があったので。そこから「つくる、つむぐ、つづく、Ameba LIFE」という言葉が生まれました。
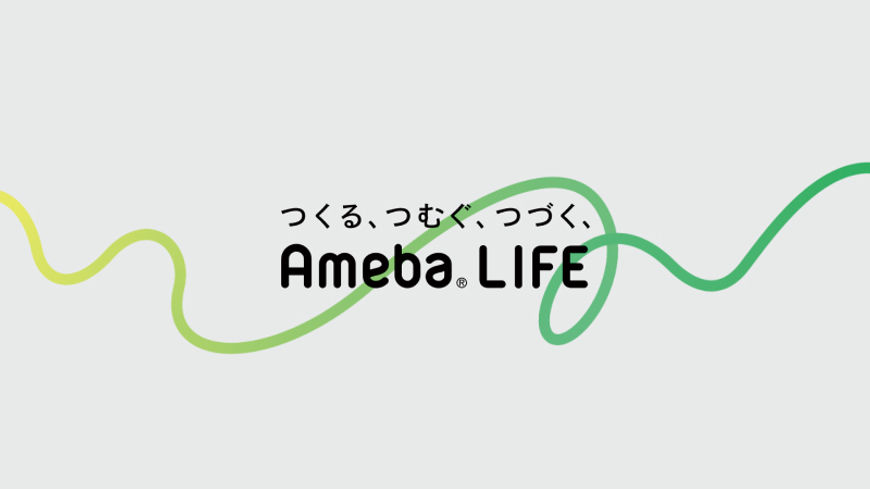
原:その言葉が生まれたのが、リブランディングの肝というか、クリエイティブの1番根幹となるコンセプトになりましたよね。この言葉で、自分自身も背負うものの覚悟が決まりました。
武本:新しいコンセプト「Ameba LIFE」は、あくまでもシンボルであって、伝えたいイメージはビジョンでありスローガン、そしてバリューにもなっている「つくる、つむぐ、つづく、」という言葉に込めました。ずっと循環していくイメージを伝えたかったので、「つづく。」ではなく、あえて「つづく、」にしています。

強度ある言葉がデザインの立ち戻る場所になる
原:「つくる、つむぐ、つづく、」はブランドビジョンでもありスローガンでもあるので、Amebaのある生活・暮らしを、我々がつくっていくというモノづくりをする時の視座に繋がっています。
武本:この言葉があったからこそ、何回も2人で話し合い、ぐるぐるとどこまでも思考して、結果的にはシンプルになりましたが、すごく奥行きのあるクリエイティブになりましたよね。
原:奥行きがあるものになったのは、アウトプットで魅せながらも、説得力のある言葉で伝えているからだと思います。
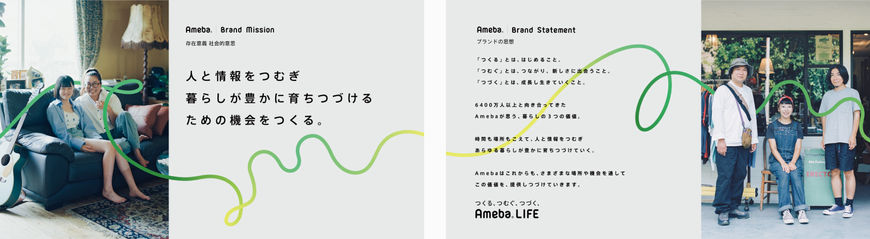
武本:デザインをする上で言葉選びにはいつも気を付けています。モノをつくる時の根幹や軸みたいなものは、感覚を広げる出発点になるので、生み出される言葉を大事にしているんです。今回でいうとブランドビジョンなのですが、未来を示すための言葉として強度が大切でした。そのような言葉たちが何かをつくる時の奥行きに繋がったりします。感覚でやっているようで、根幹となるコンセプトと表現を行ったり来たりして意味や奥行きをつくっていく感じですね。
原:感覚的でありつつ、言語化されているところが掛け算になっているので、言葉があることでつくるものを狭めるわけではなく、立ち戻れる場所になるってことですよね。表現のパターンを色々出して足し算していったんですけど、表現の軸は決まっているので、引き算されていく感じで。シンプルだからこそみんなが戻ってこられるというか。
武本:それに、クリエイティブとの掛け算で、言葉の意味がより伝わるようになるので、ブランドキービジュアルはかなりこだわりました。「20周年に向けてブランドサイトをつくって世の中に発信しよう」と一気に走り出したのもブランドキービジュアルができた辺りからで、これを機に組織全体でもリブランディングプロジェクトが動き出しました。
人々を動かすクリエイティブであることが重要
武本:「クリエイティブでどう伝えるか」は、実際のユーザーにフォーカスして、等身大の暮らしからにじみ出る空気感や表情を写真で伝えたいと考えていました。ブランドを表現するには写真の強さが重要だと思っていたので、ブランドコンセプトを体現してくれるカメラマンを探して、濱田英明さんの写真がコンセプトに合うと思ってお願いしました。
原:濱田さんに絶対引き受けていただきたかったので、撮影イメージが湧くように濱田さんの写真を提案書に入れて「撮影したいのは、こういうイメージです」と持っていきましたよね。
武本:そうですね。人にフォーカスして写真で表現することに迷いは無かったので、濱田さんにお願いできてよかったという一方で、ブログだけではない「Ameba」への進化をブランドとして伝えるためには、写真だけでは表現しきれないので、その部分を抽象化して広く捉えなければならない難しさがありました。元々ある“Amebaらしさ”を継承しつつも、新しい「Ameba」のアイデンティティを生み出し、ビジュアルに融合するところが1番苦労しました。

原:ゼロから生み出す難しさもありますが、今回は歴史あるブランドを継承しつつ新しいものを生み出す難しさがありましたよね。でもそこから「つくる、つむぐ、つづく、Ameba LIFE」を生み出して表現できたからこそ、組織のみんながすんなりと受け入れてくれて、活性化できたのではないかと思っています。
武本 確かに。周りのみんなや組織全体が新しいブランドを受け入れてワクワクしてくれて、その期待の中、リブランディングチーム各々が細部にこだわってユーザーに届けたいと動いてつくったからこそ、世の中に出した時の反応もよかったですし、それこそ「つくる、つむぐ、つづく、」を体現している感じがしましたよね。
原:今までになくて新しいと思われる、シンプルに格好よくて胸を打たれるようなものを、新しい形で表現した上で、組織を活性化できたことはすごく嬉しかったです。それまでは「とにかく格好いいものやイケてるものをつくりたい」というのが自分の中のモチベーションだったんですが、サービスやブランドの背景やコンセプトを大事にしながら、新しいものを生み出す重要さを学びました。
武本:ただ格好いいものをつくればいいわけではなく、人々を動かすクリエイティブになることが大事ですもんね。ちなみに「つくる、つむぐ、つづく、Ameba LIFE」を動画で表現したら、より空気感が伝わると思って動画もつくりましたが、ビジュアルアイデンティティである「Ameba LIFE line」の動きには相当こだわりましたよね。みんなを包み込みながらつむいでいく感じと、「Ameba LIFE line」そのものが生きている感じを出そうとして。
原:「Ameba LIFE line」は、静止画でも動いている感じを表現したいと思っていましたし、ましてや動画での動きはAmeba LIFEのアイデンティティを伝えるために重要だと思っていました。これからも「Ameba LIFE」が人々に寄り添い進化しながら、「つくる、つむぐ、つづく、」を体現していくサービスとして育てていきたいと思っています。
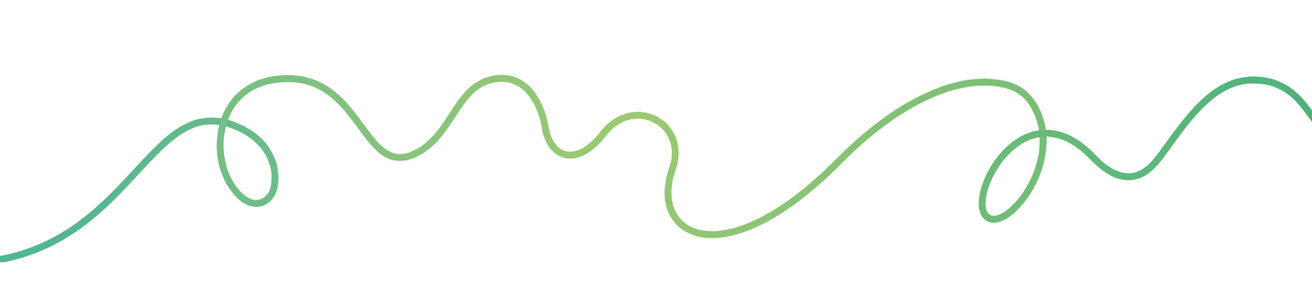
記事ランキング
-
1

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像
サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像
サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像
-
2

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...
社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代
社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...
-
3

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ
Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ
Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ
-
4

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...
【対談】ML/DSにおける問題設定術
~ 不確実な業界で生き抜くために ~

機械学習やデータサイエンスがビジネスの現場で当たり前になりつつある今、求められているのは、ビジネスの課題を実装に落とし込み、運用し、継続的な価値を生み出す視点となりつつあります。
サイバーエージェントでは、こうした実践的なスキルを持つ次世代のデータサイエンティストを育成すべく、2025年11月、新卒向け特別プログラム「DSOps研修2025」を実施しました。
「技術を社会実装する際の『問題設定』こそが重要である」 この研修のコンセプトに深く賛同いただき、特別講師としてお迎えしたのが、半熟仮想(株) 共同創業者であり、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」にも選出された齋藤優太氏です。
第1部では、半熟仮想(株) 共同創業者であり、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出された齋藤優太氏をお招きし、「ML/DSにおける問題設定術」について講演いただきました。 続く第2部では、齋藤氏に加え、当社執行役員兼主席エンジニアの木村、AI Lab リサーチサイエンティストの暮石が登壇。「現場視点×経営視点」でパネルディスカッションを実施しました。
本記事では、白熱した第2部「パネルディスカッション」の模様をダイジェストでお届けします。



