面白いゲームを作るためなら、自分にできることは何でもやる。最年少主席エンジニア就任までの道のり

サイバーエージェントでは、テクノロジー及びクリエイティブ領域において、極めて高い専門性を有し、当社に大きな貢献をもたらしている特別な人材を処遇する「主席認定制度」を2022年に導入しました。当制度の導入に伴い、最年少で主席エンジニアに認定されたのが2013年新卒入社の飯田です。
ゲーム事業を展開する子会社グレンジに所属しながら、兼務するコア技術本部ではゲーム・エンターテイメント事業部(以下、ゲーム事業部)※ を横断した様々な取り組みにおいてもエンジニアマネージャーとして活躍する飯田ですが、入社時はプログラミングの経験がほとんどなく、優秀な同期にも大きく差をつけられていたと言います。主席エンジニア就任に至った経緯を詳しく聞きました。
※ゲーム・エンターテイメント(SGE)事業部
ゲーム・エンターテイメント事業部は10社以上の子会社で構成されており、その子会社群を総称してSGEと呼んでいます。
Profile
-

飯田卓也
子会社グレンジに所属するエンジニアマネージャー。2013年新卒入社。開発の傍ら企画や進行管理業務も担い、これまでに複数のゲームタイトルの新規開発、運用に携わる。現在は、ゲーム事業部においてエンジニア組織のマネジメントを行うとともに、ゲーム全体の品質向上強化にも注力している。
自分の不甲斐なさを痛感した入社3年目
── 主席エンジニアに選ばれた際の率直な思いを聞かせてください。また、これまで築いてきたキャリアや培ったスキルを踏まえて、どのような点が評価されたと考えていますか?
嬉しく思うと同時に、非常に驚いたというのが正直な感想です。と言うのも、ゲーム事業部の中でも技術的に自分より優れているエンジニアは多くいるからです。ただ、私は組織やチーム、プロダクトをより良くするという点に大きなやりがいを感じるので、そのために自分ができることがあればという思いで、時には所属部署や職種を超えて色々な分野に取り組んできたことを評価いただいたのかなと感じています。例えば、兼務で所属しているゲーム事業部内の横断組織の一員として様々なプロダクトのパフォーマンスチューニングに携わったり(参照:「【無料公開】社内研修書籍『Unity パフォーマンスチューニングバイブル』のPDF公開&オープンソース化しました!」)、「あした会議」でも全社の技術組織が抱える課題解決のための施策提案やその実行を担ってきました。
以前主席エンジニアたちと話す機会がありましたが、皆技術とマネジメントの比重も異なるし、課題解決のためのアプローチも実に様々だったんですね。例えば、あるプロダクトのサポートに回る際、実際のプロダクトのコードを網羅的に把握した上で解決に導く方法をとるエンジニアもいましたが、私の場合は概観だけ把握した後に、メンバーとの議論を中心に進めていくことが多いです。現在主席エンジニアは全5名ですが、その多様性が実にサイバーエージェントらしいと感じました。
── 組織やチームの成長に何よりも大きなやりがいを感じるとのことですが、何かきっかけになった出来事があれば教えてください。
学生の頃先生に人生を変えてもらったと感じる経験があり、自分も誰かの成長を後押しできる存在になれたらと思うようになりました。その先生と出会うまでは勉強の面白さに気付けていなかったのですが、身に付けた知識は決して裏切らないことを教えてもらってからは勉強が楽しくなったんです。そうすると人に頼られることも増えてきて、教えることの楽しさにも気づき、教員免許も取得しました。結果的に友人に誘われて参加したサイバーエージェントのインターンシップでものづくりにさらに魅力を感じ、教員の道は選ばなかったものの、今も学ぶことが好きですし、様々な組織施策にモチベーション高く参加できるのもその原体験があるからだと感じています。
── 様々な新規ゲームタイトルの立ち上げや運用だけでなく、ゲーム事業部・全社の横断施策にも携わり、新卒入社10年目で主席エンジニアに就任という経歴だけを見ると、順風満帆なキャリアを歩んできたように思えます。これまでのキャリアで大きな挫折や苦労はありましたか?
入社時は多少プログラムを触ったことがある程度だったので、学生時代からゲームを作ったことがある優秀な同期に手取り足取り教えてもらっていました。1年目はバグが多く、苦労しました。また、ゲーム事業部がちょうどスマホゲームにシフトし始めたタイミングだったので、cocos2d-xやUnityといったゲームエンジンについても自分で学ぶしかない状況でした。
今思えば決して効率は良くなかったものの必死に働いて、技術的に互角に戦えるようになったのが入社3年目の頃です。ただ、そのタイミングで社外のプロデューサーと新規ゲームを立ち上げることになったのですが、モックを見せるたびに「これはおもしろくない」というフィードバックをいただいて。最初はエンジニアが自分1人という開発体制でしたし、毎週それが繰り返されたので非常に悔しく、自分の不甲斐なさに涙を流したこともありました。諦めずに食らいついていった結果、好評価をいただけるようになった時には嬉しかったですね。逃げ出さずに頑張って良かったと思えました。
一方で、その後にゲーム製作の経験豊富なメンバーがチームにジョインしてきて、自分の開発力はまだまだだなと思い知らされました (笑) エンジニアリング部分は主にそのメンバーに任せられたおかげで、自分は有機的な動きができるようになり、企画や進行管理など様々なことを経験させてもらいました。当時の経験や動き方が、現在のゲーム開発においても大いに活きています。
今後のゲーム開発に重要なのは、面白さに向き合う中での開発生産性
── 主席エンジニア就任後、仕事やチームへの向き合い方、自分の心掛けなどに何か変化はありましたか?
社外の方との交流が増えたという点では大きな変化がありました。モバイルゲーム業界の方々ともっと交流を深めたいと元々思ってはいたのですが、主席エンジニアに就任したことをきっかけにお声がけいただくことが増え、ありがたいです。同じ業界の様々な役職の方とお話することで新たな発見が多くあり、サイバーエージェントでさらに取り組むべきことも見えてきました。
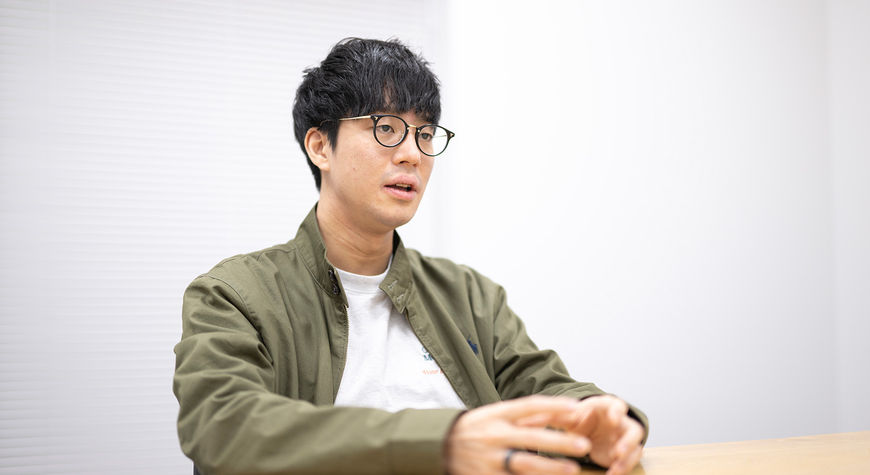
── 主席エンジニアとして、積極的に取り組んでいる課題があれば教えてください。
今まさに全社で取り組んでいることでもありますが、開発生産性とマネジメントの2点は特に力を入れていかなければいけないと感じています(参照:「AI時代においてもリーディングカンパニーを目指す、サイバーエージェントの技術戦略」「サイバーエージェント技術組織におけるマネジメント職の今」)。
昨今ゲーム開発が長期化している傾向にあるので、開発生産性についてはとりわけ課題意識を持っています。とは言っても、ゲーム開発においてはとことん面白さを追求することが市場で勝つための重要な要素であり、ある程度開発してみないとその面白さが分からないことも多いです。度重なるブラッシュアップも必要ですし、チームの合意形成のためにもあえて遠回りすることが重要な場面もあると思います。ベストプラクティスな開発については効率的に進め、ゲームの根幹に関わる複雑な部分は時間をかけて検討するなど、面白さに向き合う中での生産性がゲーム開発においては大事だと考えています。そのためには、これまでよりも進化したマネジメント形態もセットで考えていかなければいけません。
ユーザーに面白いゲームを提供するためにも、より一層会社を楽しみたい
── 今後のキャリアに悩む若手エンジニアから相談されることも多いと思います。いつもどんなメッセージを送っていますか?
最近は、「モノやコトに向き合えば良いと思うよ」と話すようにしています。キャリアについて深く考えることは時に大切だと思いますが、悩んでもやもやしても仕方がありません。闇雲に悩むのではなく、目の前のものを良くしたい、改善したいという目線で主体的に動いた方が、自ずと道は拓けると考えているからです。例えばリードエンジニアになるにはどうすれば良いのだろうと考えるのではなく、目の前のモノやコトに必死に向き合い、行動に移すことを繰り返していけば、市場価値が上がり自然とリードエンジニアへのキャリアが見えてくると思います。
── 最後に、今後の目標を教えてください。
今後もさらに面白いゲームをユーザーに提供していきたいと考えています。我々ゲーム事業部では、「世界に誇れるSGE(すげー)開発力の追求」をビジョンに掲げているので、新たな開発手法や技術基盤、チームビルディングなど日々試行錯誤することで、より面白いゲームを作れる環境を築き上げていきたいです。面白さに向き合うというのは答えのない道のりですが、答えがないからこそ、その過程を経験することは何にも変え難い財産になると思います。面白いゲームを作るために、今後も自分ができることであれば果敢に挑戦し、さらに会社を楽しんでいきたいです。

オフィシャルブログを見る
記事ランキング
-
1

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...
社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代
社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...
-
2

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」
値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」
値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値...
-
3

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...
-
4

【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」で挑む、日本アニ...
【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」で挑む、日本アニメのグローバルヒット
【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」...
【対談】ML/DSにおける問題設定術
~ 不確実な業界で生き抜くために ~

機械学習やデータサイエンスがビジネスの現場で当たり前になりつつある今、求められているのは、ビジネスの課題を実装に落とし込み、運用し、継続的な価値を生み出す視点となりつつあります。
サイバーエージェントでは、こうした実践的なスキルを持つ次世代のデータサイエンティストを育成すべく、2025年11月、新卒向け特別プログラム「DSOps研修2025」を実施しました。
「技術を社会実装する際の『問題設定』こそが重要である」 この研修のコンセプトに深く賛同いただき、特別講師としてお迎えしたのが、半熟仮想(株) 共同創業者であり、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」にも選出された齋藤優太氏です。
第1部では、半熟仮想(株) 共同創業者であり、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出された齋藤優太氏をお招きし、「ML/DSにおける問題設定術」について講演いただきました。 続く第2部では、齋藤氏に加え、当社執行役員兼主席エンジニアの木村、AI Lab リサーチサイエンティストの暮石が登壇。「現場視点×経営視点」でパネルディスカッションを実施しました。
本記事では、白熱した第2部「パネルディスカッション」の模様をダイジェストでお届けします。


