【バックエンド×機械学習向け】「ABEMA」でリアルな開発現場を体験できるインターンシップを開催!

サイバーエージェントでは、毎年趣向を凝らしたインターンシップを開催しています。今回は、その中の1つ、新しい未来のテレビ「ABEMA」を題材としたサーバーサイド×機械学習向けのインターンシップ「ABEMA Growth Tech Vol.2」をご紹介します。運営の福永と伊藤に、得られる技術スキルや、成長できるポイントなどについて聞きました。 ABEMA Growth Tech Vol.2
「ABEMA」の視聴データを元に、機械学習を用いた番組レコメンド機能をAPIに組み込むまでの一連の流れを体験できるワークショップ形式のインターンシップです。モデル形成後、そのモデルがどのように現場で使われるかを体験していただけます。
Profile
-

福永 亘
2011年入社。「アメブロ」や「ガールフレンド(仮)」、「オルタナティブガールズ」などの開発を担当。2017年9月よりAbemaTVビジネスディベロップメント本部にて、広告配信サーバーの開発などを担当。2019年より開発局局長を務める。
Twitter:wataru420 -

伊藤 可織
2020年新卒入社、「ABEMA」に配属。主に月額サブスクリプション「ABEMAプレミアム」やレンタル、有料オンラインライブ「ABEMA PPV ONLINE LIVE」等課金関連の開発に従事。今年2月に発足した改善プロジェクトにおいてバックエンドチームのマネージメントを行なっている。
バックエンドと機械学習の連携を体験
──本インターンシップでは、どのような経験ができますか?

福永
バックエンド×機械学習が、現場でどのように関わるのかを学んでいただくので、実際に働くイメージを掴めるのではないかと思っています。プロダクト開発における機械学習の導入は、ここ1~2年で一気に進みました。世の中からの見え方としては別職種だと捉えている人もいるかもしれませんが、実際には重なるところが多い。携わっている私たちだからこそ伝えられることがあると思うので、リアルな現場を体験していただきたいですね。

伊藤
加えて、「ABEMA」を運用する中でとれたビッグデータのほか、私たちが実際に利用しているパブリッククラウドのAmazon Web Services上に必要なリソースを自由に組み合わせて開発を行ってもらうので、貴重な経験になるのではないでしょうか。

福永
機械学習に興味がある人は、Kaggleなどのコンペに参加したことがある方もいると思います。そういったコンペでは、答えがある課題に対して取り組みますよね。一方、プロダクト開発においては答えがない。この違いは大きいと思います。現場では、自分で考えて答えを見つけていくことが求められる。仕事をする上での醍醐味でもあると思うので、その面白さを感じてもらえたらと思っています。

伊藤
学生の皆さんが挑戦したいことに取り組んでいただける設計にしました。最初にハンズオン形式で番組レコメンドAPIを最低限動かせる状態まで作成します。その後は、ご自身で設定した自由課題にメンターのサポートのもと挑戦していただきます。自由課題は、Terraformを使ったインフラのコード管理や、CI/CDツールの導入などを想定していて、実運用を行う中で欠かせない技術を学んでいただけたらと思っています。
また、スキルセットの幅広いメンターを集めているので、学生の皆さんが挑戦したいことに対して、しっかりサポートできる体制をつくっています。

福永
各事業部でリーダーポジションについている2~3年目の若手エンジニアをメンターとして多くアサインしていることも、こだわったポイントですね。若手の技術力やどれくらい裁量を持って働いているのかなども知っていただけると嬉しいですね。

──本インターンシップ開催に至った背景を教えてください。

福永
職域を超えていかなければ、良いものがつくれないと考えているからです。これまでは、バックエンドか機械学習のどちらかしか知らないエンジニアが多かったと思いますが、MLOpsといった機械学習とバックエンドを繋ぐ基盤が大事だということをGoogleやAWSなども提唱し始めていることもあり、世の中の注目度が高まっています。ここ数年でプロダクトにおいて機械学習の導入は当たり前に。こうした時代の変化とともに、両職種を担える人材の需要が高まってきているという背景があります。

福永
冒頭でもお話したように、機械学習エンジニアとバックエンドエンジニアの関わり方を学んでいただくことがメインではあります。加えて、今回のインターンシップでは、実運用してるサービスを1人で設計していただくので、インフラからバックエンドのことまで、幅広く学んで帰ってもらえたらと思っています。
本インターンシップを通して、サービスに対する課題をどうすれば解決できるのかと、一歩踏み込んだところまで考えてくれるようになったら嬉しいですね。

伊藤
サイバーエージェントの社風も知っていただけたらと思っています。私は2年目になったところで、まだまだ至らないところはありますが、意見を率直に言える環境があります。例え考え方が間違っていたとしても、否定するのではなく、指摘した上でどうすれば解決できるのかを一緒に考えてくれる人が多いですね。こうした心理的安全性が高い環境のおかげで、私も成長することができたと実感していますし、組織としても活性化できていると感じています。

現場で求められるエンジニアとは
──現場では、どのようなエンジニアが求められているでしょうか?

福永
勉強し続けられる人じゃないでしょうか。いろんなものに興味を持って、深堀りしていく能力が重要。楽しく続けられると尚良いですね。バックエンドの方なら、機械学習に興味を持って知識を深めた上で業務に取り組むなど、職域を自ら広げていける人が現場でも必要とされていると思います。私自身も、自分に足りないと感じた知識は、その都度インプットするようにしています。サイバーエージェントは勉強会が豊富で、プロジェクトや事業部を超えて交流があるので、入社後は、そういった機会をしっかりいかしてもらえたらと思います。

伊藤
よく言われることかもしれませんが、自走できる人材が求められていると思います。教えてもらったこと、任されたこと、言われたことだけをするのではなく、福永が言っているように、そこに付随した知識を自ら勉強する。何か問題が発生したときの対応や、新機能を開発をするときなど、日頃のそういった取り組みがいかされると思います。

福永
あとは、得た知識をアウトプットすることが大事。インプットした知識を自分に定着させることができます。特に若いときは、重要だと思いますね。GitHubやブログ、書籍、Twitter、登壇などアウトプット先はなんでもいいですが、インプットとアウトプットを続けていける人はすごくいいなと思いますね。

──どのような学生に参加してもらいたいですか?

福永
テクノロジードリブンで世の中を良くしたい、インターネットの技術を使ってもっと豊かな社会にしていきたいという思いが少しでもあれば、ぜひ来てほしいですね。大量のトラフィックをさばけるようになったバックエンドの技術など、テクノロジーの進化によって新たなビジネスチャンスをつくることができる。サイバーエージェントが提供している様々なプロダクトも多少なり世の中の人々に貢献していると思っています。こうしたテクノロジーの力で世界をより豊かにするための方法をインターンシップで学んでほしいですね。私自身も、無限の可能性を感じているインターネットを使って、世の中に貢献していくことが目標です。

伊藤
世の中やサービスの仕組みに関心がある人は、ぜひ来てもらいたいです。私自身、Webをはじめたきっかけが、「サービスの裏側をもっと知りたい」「このシステムってどう動いてるんだろう」という興味からでした。こういう好奇心はサービスを開発する上で、大切だと思うんですよね。また、「ABEMA」で実際に使われているデータや開発環境を提供できるので、大規模なサービスに興味がある人も参加していただけるといいかもしれません。
記事ランキング
-
1

「Inbound Marketing Summit」開催レポート
「Inbound Marketing Summit」開催レポート
「Inbound Marketing Summit」開催レポート
-
2

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...
-
3

「AI Worker」と自律型AIエージェントが実現する 人とAIが協働する世...
「AI Worker」と自律型AIエージェントが実現する 人とAIが協働する世界とは?
「AI Worker」と自律型AIエージェントが実現する 人と...
-
4

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来
アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来
アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと...
【後編】高い満足度とロイヤリティ向上に繋がる社内施策の考え方「CAramel サイクル」
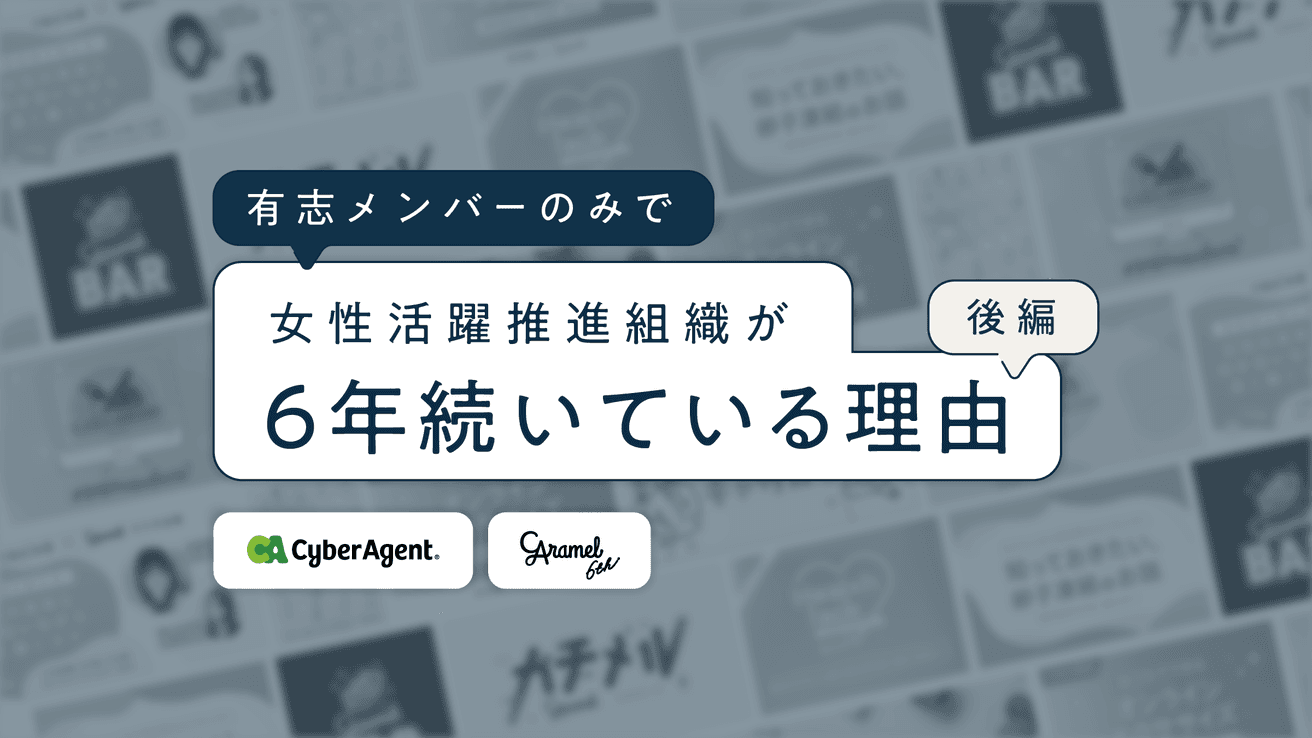
女性活躍推進組織「CAramel(カラメル)」は、2017年に発足した社内の有志メンバーで構成される横軸組織*です。
*所属部署やミッションの垣根を超えた社員で構成される、全社横断組織
サイバーエージェントで働く女性社員の課題に向き合い、これまでの6年間で数多くの施策を実施し、社内実績を積み上げてきました。
本記事では「CAramel」がどのように組織づくりを行い、満足度の高い施策を実施し続けられるのか、前編・後編にわたってご紹介します。【前編はコチラ】
これらの情報が、各企業の女性活躍支援・ダイバーシティ推進プロジェクトのご担当者や、有志メンバーによる組織運営の一助となれば幸いです。




