エンジニアが推進した、5000人の社員をつなぐ
Slack Enterprise Gridプロジェクト

サイバーエージェントではSlack Enterprise Gridを活用した社内のコミュニケーション効率化を図っています。本プロジェクトを推進したエンジニア3名のインタビューから、サイバーエージェントのカルチャーや、全社横断プロジェクトの様子をお伝えします。
Profile
-

大倉 香織 (技術政策管轄 CyberAgent Dev Center)
2006年にサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。メディア事業のサービス開発に携わり、メディア事業のエンジニア開発環境の整備を推進。2021年4月からは、メディア事業からCAグループ全体へとスコープを広げ、技術資産をより効果的に活用していくミッションを担う。 -

黒崎 優太 (AI事業本部/DX本部 アプリ運用センター)
2015年にサイバーエージェント入社。スマホアプリ向けの広告配信プラットフォームであるDynalystの開発責任者として従事。
2021年よりDX本部アプリ運用センターのバックエンド開発とセキュリティも担当。
AI事業本部へSlack GridやGithub Enterprise Cloudの導入も行った。 -

石黒 祐輔 (株式会社QualiArts 開発推進室)
2014年にサイバーエージェントに入社。Amebaゲーム(現QualiArts)の基盤開発チームにUnityエンジニアとして配属。現在は、QualiArtsにて基盤全般のリードをしつつ、ゲーム事業部全体の開発基盤の強化にも従事。Slackに関しては2018年頃からゲーム事業部全体のSlack化とその後Grid化を推進。
「自分たちで会社を良くする」カルチャー
ー サイバーエージェントではどのようにSlackを運用していますか?

大倉
私の所属するメディア事業部では、 2014年頃からSlackを業務に利用するプロジェクトが増えてきました。Slackは使いやすさや柔軟な拡張性から、技術者のカルチャーに定着する一方で、部署や子会社それぞれで運用していたため、ワークスペースを横断した情報交換やコミュニケーションまでには発展していませんでした。
また、複数のワークスペースに複数のアカウントで対応する煩わしさや、社員の入退職に際してのアカウント管理が課題になっていました。
2017年頃に一度、ワークスペースの統合ができるSlack Enterprise Gridの導入を試みたのですが、他の事業部ではまだSlackが積極的に業務活用されていなかったのもあり、導入を見送った事もありました。

大倉
トップダウンで「このツールを業務で使ってください」といった導入をしないのがサイバーエージェントの企業カルチャーです。特に、チャットツールは技術者が愛用しているのもあり、支持されていればプロジェクトに積極的に活用されるし、支持されていなければ仮にトップダウンで決めたとしても、浸透しないんですよね(笑)。

石黒
私の所属するゲーム事業部では、技術者の中で既にSlackが浸透していたものの子会社としては別のチャットツールを利用していたため、エンジニア発で経営層の決裁を取り、チャットツールを一斉にSlackへ移行しました。その際、TEC8(ゲーム事業部横断のエンジニアボード組織)である自分が音頭を取りつつも、子会社をまたいだエンジニアが協力しあって推進しました。

黒崎
AI事業本部でも、エンジニアがSlackで技術交流やコミュニケーションをとっていて、特に「times」と呼ばれる雑談チャンネルが活発です。日頃からエンジニアが考えている事や、技術的な興味関心、会社の制度や施策について議論しているので「times文化」と呼ばれたりしますが、経営陣やビジネス職もそれぞれのtimesに興味をもつようになり、Slackが職種を問わず浸透していきました。

大倉
このように、それぞれの部署でSlackが浸透してきたので、あらためて「Slack Enterprise Grid」を全社導入できないかと、エンジニア有志で「Slack Enterprise Grid導入プロジェクト」が発足しました。

ー 現場のエンジニアが主導で全社導入を推進するのはユニークですね

黒崎
各事業部のエンジニアが導入し始め、使い勝手の良さから浸透していったSlackが、次第にオフィシャルなポジションになっていくプロセスは、サイバーエージェントらしいカルチャーだと感じます。

石黒
ゲーム事業部には「自分たちの会社は自分たちで良くする」という考えがあります。Slackを事業部オフィシャルのチャットツールとして正式導入する際も、予算や導入をエンジニアボードに任せてくれたのが印象的でした。
トップダウンで「明日から業務ではSlackを使ってください」という導入になると、別のチャットツールを使っている人は混乱しますし、コミュニケーションのロスが発生してしまいます。チャットツールを導入する目的は「良いゲームを開発するため」であって、メンバーに生産性の向上や使い勝手を実感してもらわないと意味がありません。
その点、大倉さんの言うように「ツールが支持されている事」が前提なのは重要になると思います。

大倉
2020年の春頃にメディア事業部とゲーム事業部が、既存のワークスペースを「Slack Enterprise Grid」に統合しました。そして2020年7月月にAI事業部が統合しました。それ以外の事業部や各部署もそれぞれのタイミングで参加しています。
グループ全体で一斉に統合したわけではなく、事業部単位で五月雨式に参加していきました。ここもサイバーエージェントらしいカルチャーでしたね(笑)。

黒崎
他の部署がSlack Enterprise Gridに統合すると、ワークスペースをまたいだ部署/子会社連携が進んでいくんですよね。その便利さから「うちも検討しようか」という流れになるのがサイバーエージェントらしいですよね。
ある部署のSlack Enterprise Grid説明会に、他部署の人が参加したのがきっかけで、検討のきっかけになったりもしました。
Slackに限らず、ライブラリやフレームワークの導入は、評判や現場の声を元にボトムアップで導入されていくのが会社のカルチャーです。だからこそ「安心感や便利さ、使い勝手の良さ」が重視されます。

Slack Enterprise Grid導入で加速した技術のスケールアウト
ー 導入後のコストメリットはどうでしたか?

大倉
メディア事業部は、7つか8つぐらいのワークスペースが事業部内にあり、複数のアカウントで対応している人が非常に多いのが現状でした。私も5つぐらい持っていましたが、その5つのアカウントを1つにまとめられるだけでコスト減につながります。部署によっては大幅にコスト削減に至った所もありました。
また、Slack Enterprise Gridを導入する事でアカウントが一元管理されるので、会社の人事データベースと連携できるようになり、アカウントの統制をしやすくなりました。
それまでは、入退社に関するアカウント管理を部署ごとに運用していました。セキュリティ推進グループが一元管理する事で、抜け漏れもなくなり、セキュリティリスクもカバーできます。SSOでログインできるので社員の利便性も上がりました。

石黒
部署や子会社を横断したコミュニティ活動や採用活動はSlackを通じて活性化しましたね。特に子会社内で閉じがちだった技術情報が、言語やプラットフォーム別に作られたチャンネルがきっかけで、全社での技術交流が活発になりました。
また、表彰などの事業部横断イベントがある際は、実況チャンネルが作られて盛り上がるなどをしています。

黒崎
他部署との技術連携は加速しましたね。#ca-tech-kubernetes や #ca-tech-rust といった「#ca-tech-****」といったチャンネルができて、技術連携や情報交換が活発になりました。サイバーエージェントにはグループ全体で、技術者が2000人近く在籍しているので、関心度が高いトピックなら、書き込めば誰かしら何かを教えてくれる環境は強みです。
技術交流という点だと、雑談チャンネルは非常に活発です。「#*times_***」と付くチャンネルだけでもグループ全体で1000以上あります。ここでのつぶやきが技術的なヘルプやサポート、更には社内の施策や組織への提案、プロダクト連携につながるケースが増えています。

大倉
Slack Enterprise Gridに人事系や労務系などコーポレート部門が参入した事で、様々な職種での利用が広がったのと、Slackを活用して業務の自動化や効率化が進んだのも効果的でしたね。
オンライン勤怠の通知等もコーポレート部門と連携して進めさせてもらっています。

エンジニアもコスト感覚を大事にしていきたい
― 今回のプロジェクトに参加して、エンジニアとして成長した事は何ですか?

大倉
契約周りとコスト管理は本当に大変でした(笑)。
契約やコスト関連は、一見するとエンジニアが避けがちですが、今回のプロジェクトが成功したのは、エンジニアがコストをしっかりと見てバックオフィスと調整をしたことが大きな要因だったと思っています。「ツールを全社に導入したいので、契約とかコスト管理の部分はコーポレート部門の人にお任せします!」というスタンスでは成功しなかったと思います。
コミュニケーションツールは日常的に使われるので、各事業部間で合意形成したり役員の承認を得る必要もありますし、そのために色々な材料を集めてプレゼンテーションも求められます。それはエンジニアが苦手とする分野ですし大変な作業でもありますが、ビジネスとしてプロジェクトを推進するためには、職種を問わず大事な事だと改めて思いました。

黒崎
割引交渉も今回のエンジニアメンバーが中心になってやりましたが、そもそもエンジニアの本業である技術的な部分ではないですからね。でも、忍耐が求められる価格交渉をやってでも実現したいというメンバーが集まっていたのは良かったと思います。

石黒
といっても、インフラ系の人たちはもともとコスト意識は高いですよね。ベンダーとの価格交渉も日常的にやっているようですし。

大倉
私も元インフラエンジニアなので、契約書や予算管理に触れていたこともあって、苦労半分、懐かしさ半分だったかも(笑)。そこまで苦手意識はなかったかな。

黒崎
私はコスト管理にがっつり関わったのは初めてだったので、とても勉強になりました。年間で大きなお金がかかるプロジェクトを推進するには、誰に相談すれば背中を押してくれるのかなど(笑)。

大倉
「このツールは便利だから導入したい」というエンジニアならではの提案で、柔軟にプロジェクトにそのツールが採用されるのがサイバーエージェントの良さです。
その一方、全社にそのツールを浸透させるフェーズになった際に求められるのが、組織間の合意形成や投資対効果などのコスト面、セキュリティやアカウント管理などのガバナンス面のハンドリングです。
今回、エンジニアが有志で集まって作ったプロジェクトが成功した要因は、自分たちの専門分野から一歩踏み出して、そういった組織マネジメントやガバナンスにチャレンジし、他部署や多職種の理解と応援を得られたからだと思っています。
まさに「自分たちの会社は自分たちで良くする」というカルチャーを実体験できたプロジェクトでした。

オフィシャルブログを見る
記事ランキング
-
1

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来
アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来
アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと...
-
2

クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェントが支援する「...
クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェントが支援する「AI×制作プロセス改革」の最前線
クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェ...
-
3

企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的AIリーダーが語...
企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的AIリーダーが語る最先端戦略「AI SHIFT SUMMIT 2025」開催へー
企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的...
-
4

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...
アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来
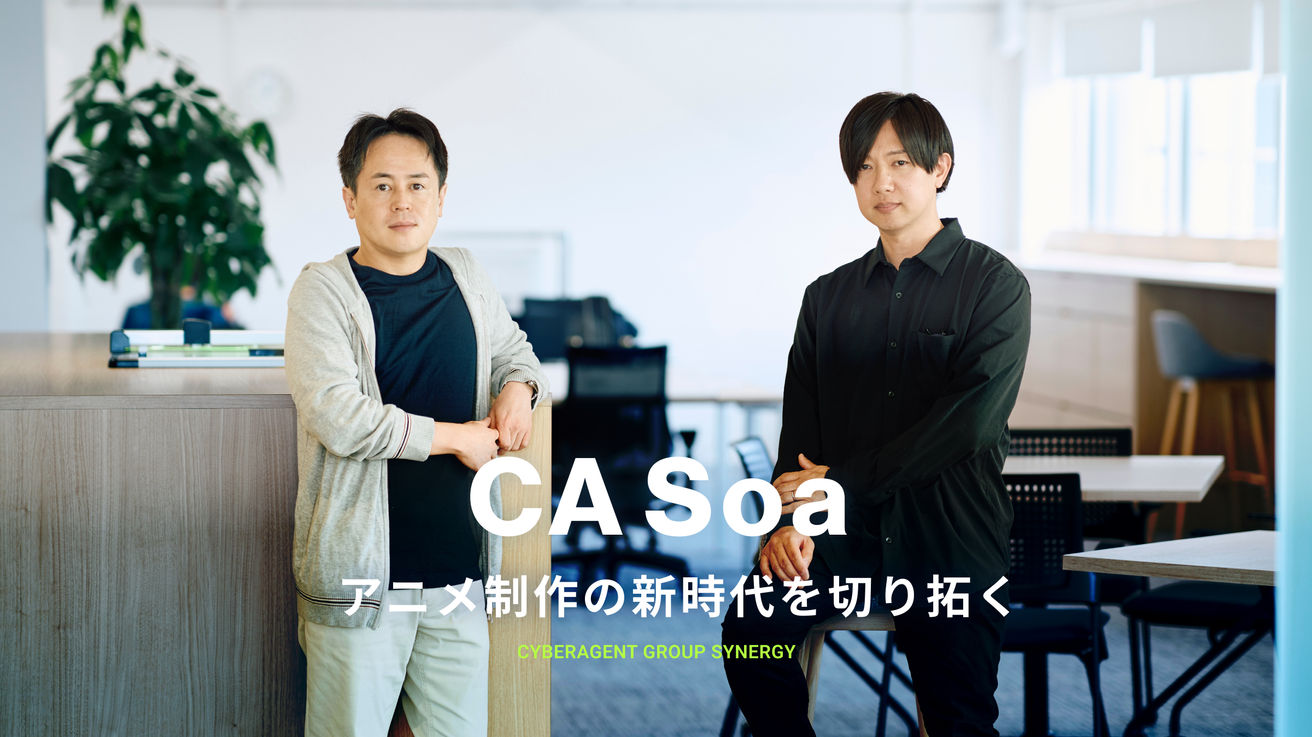
世界市場で存在感を増す日本のアニメ。その制作現場において、クリエイターの情熱を土台としつつ、より良い創作環境や制作プロセスへの期待が高まっています。
サイバーエージェントは、この期待に応え、アニメ業界の持続的な発展に貢献すべく、新たなアニメ制作スタジオ「CA Soa」を設立しました。
「クリエイターが真に輝ける環境」と「テクノロジーによる制作プロセスの革新」を掲げ、同社代表でアニメプロデューサーの小川、アニメーター有澤が描く“理想のものづくり”とは。設立の想いと未来への展望を聞きました。


