ANA Xとサイバーエージェント、異業種タッグが築く「ANA Moment Ads」 売上3倍を実現した二社融合の軌跡

異なる企業文化を持つANA Xとサイバーエージェントが、協業を開始して3年半。単なるビジネスパートナーシップに留まらず、両社のメンバーが「ワンチーム」となってプロダクトをゼロから共創してきました。
本記事では、事業責任者と開発責任者が、初年度から売上3倍の成長を実現したデジタル広告配信事業「ANA Moment Ads」の成功の裏側を語りました。事業の根幹にある「三方良し」の思想から、両社の組織能力の強化を体現する協業の真髄に迫ります。
目次
事業の魂を宿した「三方良し」を体現する、安心・安全なプロダクトを
桁違いの開発スピードと技術力。「こんなあっさり変えてしまうのか」
文化の壁を越えて。「プロジェクトルーム」から生まれたワンチームの正体
決め手は「ゼロからものづくりを共にする」パートナーシップ
― まず、ANA X社が数ある企業の中から、当社をパートナーとして選ばれた決定的な理由は何だったのでしょうか。
ANA X 住吉氏:コロナ禍で何か新しい事業を、という中でデジタル広告事業がテーマに上がったのですが、本当に何もできない状態からのスタートでした。グループ内にノウハウがない。もちろん、いくつかお声がけした会社はありました。
その中で、サイバーエージェントさんだけが「ゼロから事業を一緒に作りましょう、一緒にチャレンジしましょう」と言ってくれた。この“ものづくりから一緒にやってくれる”という点が我々としては非常に有り難く、惹かれました。

コロナ禍を機にANAグループの資産であるデータを活用した新規事業として、デジタル広告事業の立ち上げを牽引。本協業における事業全体の責任者として、プロジェクトを推進している。
ANA X 住吉氏:広告事業のトップランナーであると同時に、テック企業としての開発力を兼ね備えている。そして、営業の素人集団である私たちに対し「人材の育成も担います」とまで言ってくれた。その熱量というか、「自分たちも一緒にこれを作るんだ」という当事者意識がメッセージから強く響いてきて、「他社とはできないことをやってもらえる関係になれるんじゃないか」と。それが決定的な理由ですね。
― 三浦さんは、この協業のお話を聞いた時、どのような可能性を感じましたか?
三浦:もう、率直にワクワクしましたね。当社はインターネット広告やメディア、ゲームといった自社プロダクトで成長してきた会社です。その我々が、日本を代表する事業会社であり、航空業界の雄であるANAグループと協業できる。しかも、その形が営業やコンサルティング支援ではなく、ゼロから一緒に「新しい市場」を創り上げていくという壮大なものだった。このスケールの大きさと、これからの未来に、ただただ楽しさを感じました。
またこれまでのインターネット広告で活用してきた過去データとは大きく異なり、ANAグループが持つ航空予約データは、「確実性の高い将来の移動データ」で、未来の行動情報という点に新たな可能性を感じました。

2015年にサイバーエージェントへ中途入社。アドテクプロダクトの事業責任者を経て行政DXおよび協業DXの立ち上げを経験。本協業において、サイバーエージェント側の事業責任者を務める。
事業の魂を宿した「三方良し」を体現する、安心・安全なプロダクトを
― 協業開始からこれまで、特に記憶に残っている出来事や転機があれば教えてください。
ANA X 住吉氏:私の立場からすると、2023年11月の「ANA Moment Ads」サービス提供開始の記者説明会を共同で行った時が、一つの大きな区切りであり、本当の意味でのスタートだったと感じています。業務提携開始から1年半かけてプロダクトを準備し、お客様へのヒアリングを重ねてきたものを、初めて世の中にお披露目する日でした。自分の言葉で、このプロダクトが単なる広告ではないというメッセージを伝えられたのは、非常に感慨深い経験でした。
私たちが目指すのは、広告を見ていただくユーザー(ANAマイレージクラブ会員)、広告を出稿していただく企業、そしてその中心にいる私たち、その三者すべてがハッピーになる「三方良し」のスタイルです。このプロダクトの魂とも言える想いを、あの場で語れたことが、私にとっては非常に印象的な出来事です。この「三方良し」は、今でも私たちが立ち返るべき原点になっています。
三浦:これまでもプロダクトのプレスリリースを出した経験はありましたが、今回は全く反応が違った。これまでは広告業界からの反応がほとんどでしたが、今回は特に旅行業界や航空業界のメディア、企業の方々から大きな反響があったんです。
いわゆる「DX」という掛け声だけで終わらせるのではなく、実際にデータを活用した事業を創り上げたことで注目を集めたのだと考えています。他事業会社との広告事業創出支援の協業事業は小売業界を中心にスタートしましたが、現在ではANA X社をはじめ、通信・金融・ヘルスケアなど小売以外の様々な業界にも広がっています。「事業会社の広告会社化・広告事業立ち上げ」が改めて大きなトピックスとして受け止められた結果だったのではないかと思います。
もう一つ、営業面で印象的だったのは、この事業が「デジタルでありながら、非常にリアルなビジネスだ」と感じる瞬間が多いことです。管理画面の数字だけではない、リアルなビジネスの手触りを感じます。広告の先には、旅行者という「人」がいる。このデジタルとリアルの融合が、この事業の面白さだと日々感じています。
―本協業における具体的な事業的成果はどのようなものですか?
ANA X 住吉氏:「ANA Moment Ads」を提供してまもなく2年、事業的な成果として、前年度と比較して売上が3倍に成長しました。
数値上はまだ発展途上ですが、私たちは単なる広告事業の成長だけでなく、ANA Xの旅行事業との連携によるシナジー創出も目指しています。
実際に、宿泊事業者様など、事業パートナー企業が「ANA Moment Ads」を活用し始め、広告を見たユーザーが実際に施設を訪れるといった成果も出てきています。
これは、私たち広告事業だけでなく、広告主企業、そしてユーザーも新しい旅のきっかけを得られるという、まさに「三方良し」の形が生まれつつあることを意味します。この「お客様に価値があると感じて使っていただけている」事実は、数字以上の大きな成果だと感じています。
―多くの企業や顧客が関心を持つ個人情報の取り扱いについて、本協業ではどのような配慮をされていますか?
ANA X 住吉氏:リリースが当初の予定より遅れた一因は、法務面での慎重な調整でした。弁護士の確認を重ね、規約も複数回改訂しました。技術的にも個人情報を扱わない仕組みを徹底し、法律に準拠した形でサービスを設計しています。
三浦:各国の法制度に準拠した対応が必要となるインバウンド向けの広告配信は、十分に整備できるまでは敢えて踏み込まない判断をしました。安全性を優先した結果でもあります。
桁違いの開発スピードと技術力。「こんなあっさり変えてしまうのか」
― テクノロジーの面で、「サイバーエージェントだからこそ」と感じられたのはどのような点でしょうか?
ANA X 森氏:驚きの連続でしたね。まず、アドテクノロジー領域の知見を活かして、非常に大規模なシステムを驚くほど低コストで運用できる点。これはシンプルにすごいなと。
そして、何より開発のスピード感です。私も前職はベンチャーでスピードには自信があったのですが、次元が違いました。特に違うのは「リリースの頻度」。以前の感覚だと月2~3回リリースできれば速い方でしたが、ここでは月に30回ある。本当に桁違いです。システムは実際に本番環境で動かさないと見えてこない課題も多いので、この細かく頻繁にリリースを繰り返すスタイルは、非常に合理的で優れたやり方だと感じています。

本協業プロジェクトのエンジニア第一号としてANA Xに入社。当社のエンジニアチームと共に、広告プロダクト「ANA Moment Ads」の開発をリード。内製化に向けた組織づくりの中心的役割も担う。
―「ANA Moment Ads」開発で特に成功した事例や、その裏側にあった強みの掛け合わせを教えてください。
ANA X 森氏:特にインパクトがあったのは、「ANA Moment Ads CR(クリエイティブ)」という機能です。これは、ANAグループの持つ未来の行動データ(航空券の予約データ)を活用して、広告を単なる情報提供ではなく、よりパーソナルなものへと進化させる機能です。
具体的には、広告を見たユーザーに対してクリエイティブの一部を動的に変化させるものです。これにより、ユーザーは「これは自分に向けられた情報だ」と気づきやすくなります。
この機能の構想は開発初期からありましたが、実現には各部署の連携が不可欠でした。サイバーエージェント社の開発力に加え、ANA Xのデータ基盤を支えるR&D部門、そして複雑なフローを調整したデジタルマーケティング担当者など、関係各所の尽力があったからこそ実現できたと考えています。
今後もこの機能には発展の余地がたくさんあるので、さらに進化させていきたいです。
— サイバーエージェントとして、ANA X社の事業に対し、開発面でどのように貢献したとお考えですか?
森:当社の強みである「1st Party Dataを活用した広告配信」の知見が大きく貢献できたと考えています。これまで30以上のアドテクプロダクトを開発し、広告配信に重要なデータ設計と仕組みづくりで圧倒的な優位性を持っています。その経験とノウハウを開発の上流工程から活かすことで、迅速な開発を実現できた点が貢献につながりました。
また、プロジェクトメンバーのチームワークや連携に関しては、開発チーム内でメンバー間の垣根をなくし「ワンチーム」として動くことを常に意識していました。例えば、全員が同じ会議に参加することで、情報格差が生まれないようにしていました。
経験豊富なエンジニアが多かったため、一人ひとりの意見を尊重し、各自が自律的に動けるような、自由で対等な関係づくりを心がけました。

2021年にサイバーエージェントへ新卒入社。本協業における開発チームの責任者。アドテクノロジー領域における当社の知見を活かし、プロダクト開発をリード。ANA Xのエンジニア採用や育成にも深く関わっている
文化の壁を越えて。「プロジェクトルーム」から生まれたワンチームの正体
― 異なる企業文化を持つ両社が、一つのチームとして機能するために、どのような工夫をされたのでしょうか。
三浦:まず最初に取り組んだことは、物理的な「プロジェクトルーム」を当社のオフィス(アベマタワーズ)内に設けたことです。本協業は2022年4月頃に始まったのですが、週に1~2回のオンラインミーティングだけでは、本当の意味での融合は生まれないだろうと。フィジカルに一緒にいる環境を作ることが不可欠だと考え、こだわりました。これが結果的に、両社のメンバーが自然に会話し、協力し合う「ワンチーム」の土台になったと思います。
あとは、カルチャーの融合も意識的に行いました。まず当社の目標設定施策「プロレポ」を、ANA Xの皆さんと一緒に対面で行いました。私自身も中途入社者として、サイバーエージェントの良いカルチャーを吸収してきた経験から、この取り組みを強く推進したのを覚えています。プロレポの参加は次回が4回目と継続して実施しており、組織文化としても浸透し始めてきました。また、制作したポスターはANA X社オフィスにも掲示いただき、ANA X内で「広告事業チームがどんなことをしているのか」、「どんな世界を目指しているのか」を他部署にも知っていただくことも強く意識しています。
また、パーカーやステッカーなどのプロダクトロゴ入りグッズを作ったり、一緒に初詣に行ったりなど、交流機会も多く設けることで、より深い絆が生まれました。こうした定性的な取り組みが、異なる企業のメンバーが心を一つにした「ワンチーム」を形成する上で、非常に重要な役割を果たしたと感じています。

ANA X住吉氏:ANAグループのイベントに三浦さんに参加していただいたり、チーム全員でANAグループの研修施設「ANA Blue Base」の社会科見学も行いました。逆に私たちがサイバーエージェント社の「極AIお台場スタジオ」を見学させていただくなど、互いの会社のカルチャーやバックボーンを知る機会を積極的に設けたのも良かったですね。
「帝国を作って欲しい」から始まった内製化と、協業が生んだ組織能力の強化
― 本協業はデジタル人材の育成や採用、つまりANA X社の組織能力強化にも寄与していると伺いました。
ANA X住吉氏:その通りです。正直、私たちは何も持っていませんでした。仕組みもなければ、当然、技術者もいない。森(勇樹)さんには、エンジニア第一号として入社してもらう時に、「ゼロから“森帝国”を作ってくれないか」とお願いしたくらいです。
エンジニアの採用において、我々ビジネスメンバーではスキルセットを正しく評価できません。そこで技術面での選考に際しては、サイバーエージェント社のエンジニアの方々にも「評価観点」や「面接時の質問設計」などの観点でご協力をいただきました。その知見をもとに、ANA Xとしての採用基準を磨いていった形です。
その際に「技術は後からでも学べる。大事なのは、自分で新しいことを吸収したい、学びたいというモチベーションだ」とアドバイスいただいたことが印象的でしたね。採用プロセスの中で、技術力だけでなくカルチャーフィットまで重視する姿勢を共有できたことで、最高の仲間を迎えることができたのは大きな成果です。
ANA X 森氏:私自身もエンジニア採用のノウハウを日々学ばせてもらっています。おかげさまで、11月には新しい仲間も入社予定です。これからルールや枠組みを作っていく手触り感があって、非常に楽しみです。

森:データ活用の文脈でお話しすると、この事業においてはANAグループが保有するデータが極めて重要な役割を果たしています。
当初は、サイバーエージェントの開発チームから「このデータを活用したい」とご相談し、ANA X社よりご対応いただく場面が多かったのですが、協業を進めるにつれて、ANA X社のデータ基盤やオウンドメディアを管轄されるチームとの間で、より密接かつ双方向のコミュニケーションが生まれるようになりました。
現在では、「こういったデータがあるが、広告事業において活用価値はありそうか」といった提案をいただく機会も増えています。こうした変化を見ていると、単なるデータの受け渡しを超えて、データビジネスのプロフェッショナルとしての我々の知見や視点が、ANA X社内においても段階的に醸成されていく効果をもたらしていると考えています。
広告事業の枠を超え、旅行業界の変革へ。ANA Xとサイバーエージェントが描く未来
― 最後に、この協業事業を通じて、どのような未来を描いていらっしゃいますか?
ANA X 住吉氏:まずは、この事業を我々自身で回せるように、内製化に向けた人の育成が第一です。そしてもちろん、広告事業として、この3倍に伸びた成長カーブをさらに加速させていきます。
ただ、私たちの視野はそこだけにはありません。この事業の根幹にある「三方良し」の精神をANA Xの他事業にも波及させ、会社全体に良い効果をもたらしたい。そして、将来的には広告ビジネスという枠組みを超えて、旅行業界全体の変革に挑戦したいという大きなテーマを持っています。
現在の旅行業界では、OTA(オンライントラベルエージェント)が大きな存在感を持っています。その一方で、私たちは自社のプロダクトを通じて、従来の仕組みに新しい風を吹き込み、業界全体にポジティブな変化を起こせるのではないかと本気で考えています。
三浦:まずは広告事業として、旅行業界の企業・自治体のみなさんが使い続けてくれる「ローカルプラットフォーム」※を目指していきたいです。それに新機能なども目下開発中です。
この協業が成功することで、当社にとっても大きな財産が残ると信じています。外部の素晴らしい企業様と深く組むことで、我々だけでは得られなかった知見や経験を得ることができた。この成功体験を、広告事業とは別の領域のパートナーシップにも活かすことで、より大きな協業パートナーとなれればと考えています。
※1st Party Dataを保有している各事業企業による広告事業を指す
森:米国では、ウォルマートやユナイテッド航空といった事業会社が自社の1st Party Dataを活用した広告ビジネスを本格展開しています。日本国内でも同様の潮流が始まりつつある中、この協業事業を通じ、大規模な顧客基盤を持つ企業がデジタル広告事業を確立する成功事例として、デジタル広告や航空・旅行業界の変革を牽引できる存在となることを目指しています。
ANA X 森氏:開発者としての視点では、この協業が、日本の伝統的な大企業が内製化開発を進めていく上での、一つの優れたモデルケースになれるのではないかと期待しています。特定の強いアセットを持つ企業と、最新のテクノロジーを実装できる企業が手を組むことで、これまでにない新しい価値を生み出していく。このモデルが成功することを証明し、停滞感のある日本経済を打破する一助になれたら、これ以上嬉しいことはありません。
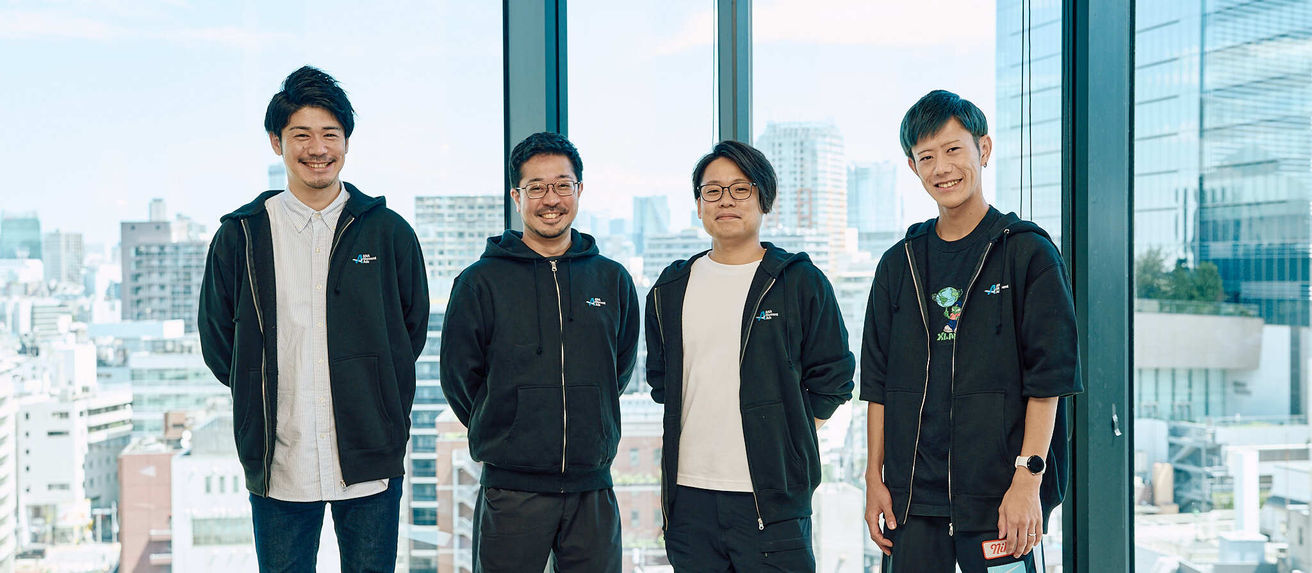
記事ランキング
-
1

【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」で挑む、日本アニ...
【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」で挑む、日本アニメのグローバルヒット
【対談】山内隆裕×岡田麻衣子 「クリエイティブファースト」...
-
2

値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」
値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」
値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値...
-
3

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...
社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代
社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...
-
4

【対談】岡田麻衣子×亀田祥倫 Studio Kurmが挑む「持続可能な」アニ...
【対談】岡田麻衣子×亀田祥倫 Studio Kurmが挑む「持続可能な」アニメの次代
【対談】岡田麻衣子×亀田祥倫 Studio Kurmが挑む「...
値引きの常識を問い直す。サイバーエージェントが仕掛ける「値引き革命」

原材料や人件費の高騰が続くなか、企業は値上げや値引きの見直しを迫られている。
「貴社が投じている販促費、その70%は利益や顧客育成への投資に変えられるかもしれない」
もし経営者であるあなたが、こう告げられたとしたらどう感じるだろうか。にわかには信じがたい話に聞こえるかもしれない。しかし、それはすでに現実になりつつある。
DXやAI活用が叫ばれる一方で、マーケティングの4Pの中でも「価格(Price)」は、長らく手つかずの領域だった。だが今、AIと経済学によってこの“聖域”を経営レバーとして捉え直し、販促費のムダを削減しながら成長投資へと組み替える道が開かれている。私たちはこの取り組みを「値引き革命」と呼んでいる。
本記事では、長年の広告運用で培った当社の実装力とアカデミックな経済学の知見を融合させ、値引き革命に取り組む「価格エージェント」事業責任者の藤田光明と、DXダイレクトビジネスセンター統括の會澤佑介に、その本質と未来、そして彼らが「やらない理由はない」と断言する理由を聞いた。

