研究者の「熱量」を「事業インパクト」へ、 AI Labの組織的アプローチ

急速な技術進化の波に乗り、研究開発組織「AI Lab」は設立からわずか9年で当社のイノベーションを牽引する組織へと成長しました。研究開発組織でありながら、論文発表にとどまらず、研究成果を着実に事業化し、社内外に大きなインパクトを与え続けています。
なぜAI Labは、これほどまでに実践的なイノベーション創出に成功しているのか。本記事では、その特徴的な取り組みを紐解きながら、当社のイノベーション創出プロセスの秘密に迫ります。
AI Labが生み出すイノベーションの原動力
AI Labが誕生してから9年。AI技術を“現実の価値”に変換する存在として、AI Labはめざましい成長を遂げてきました。 当社のAI Labが成し遂げてきた最大の実績は、研究成果を迅速にビジネスへと展開し、社会実装に直接つなげる“実装力”です。研究開発組織と聞くと、一般的には学術研究が主役であり、事業部門とは距離があるイメージを持たれがちです。
しかしAI Labは、壁を取り払い研究と事業を結びつける存在に進化しました。その要因としてまず挙げられるのが、「自発的な組織づくり」の文化です。 研究者自らが新たな価値創造に向けアイデアを出し合い、施策を決め、必要なら即行動につなげています。この自律的な土壌が、事業側からも研究側からも“価値ある研究”を生む好循環を生み出しています。
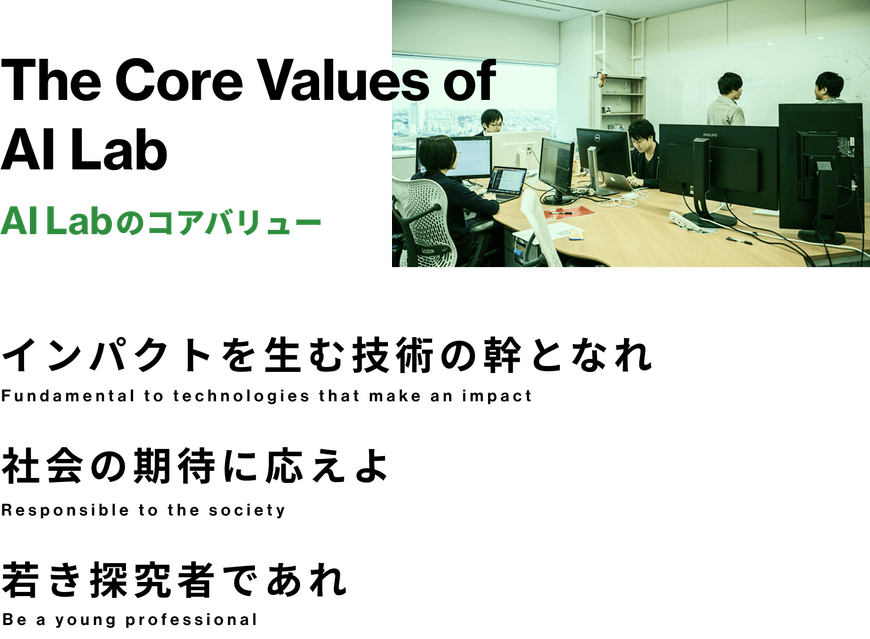
研究と事業を近づけるカルチャー
AI Labでは社会実装を強く意識し、研究者と事業責任者が直接交わる場を多く用意しています。 象徴的なのが、各研究領域のリーダーと実サービスの事業責任者による合宿の開催です。ここではビジネスリーダーが研究内容を深く理解し、研究者側も「事業の未来」や事業責任者が何を求めているのかを知る絶好の機会となっています。この濃密な対話を重ねることで、従来の「研究組織=隣の部署」ではなく、“事業の推進役”としてAI Labが機能しやすい環境が整っていきました。会話の端々から新たなプロジェクトの火種が見つかり、社会実装事例が生まれています。
また、AI Lab内で企画・実行される「AI Labあした会議」※ は、研究者自らがチーム単位で組織や事業への提案を行い、その場で実行案として決議される独自の取り組みです。ただ課題を上から与えられるのではなく、一人ひとりが「自分ごと」として組織づくりに参画し、ダイナミックに変化する研究現場の文化形成も進んでいます。
※あした会議…サイバーエージェントの「あした(未来)」に繋がる新規事業や課題解決の方法などを提案、決議する会議。そのAI Lab版を実施。
自発性を引き出す制度設計
AI Labの強みは、単なる上下関係や目標管理制度に頼らずに「内発的な成長意欲」を自然と引き出す制度設計にあります。その象徴が、ラボ内の委員会制度です。
研究者自身が研修、イベント運営、OKR※設定などの委員会を率先して立ち上げ、運営しています。
目標設計と管理を通してチームやAI Lab全体での大きな成果の創出を目指す「OKR委員会」、研究者間の交流・議論の場をつくる「イベント実行委員会」、研究開発力の底上げやナレッジのオープン化・スケール化を目指し、勉強会やワークショップを主体的に開催する「研修委員会」など、役割は多岐にわたります。
単なるAIの技術研鑽だけでなく、”事業現場で活きるコミュニケーション”や”PoC設計”といった社会実装に直結するスキルまでを網羅的に学び合う研究者向けのスキルアップ研修における資料は、外部メディアにも取り上げられるなど、社外からも大きな反響を呼びました。
※Objectives and Key Resultsの略。目標設定・管理のためのフレームワークの一つ

また2024年には、研究チームごとが成果と技術を紹介しあう「AI Lab Showcase」をサイバーエージェント全社向けに初開催、数百名が参加しました。ビジネス側メンバーも多数参加し、気軽な交流の中から新たなコラボや相談が急増しています。こうした主体的なイベントが継続し、さらに全社規模のAIイベントにも積極的に協力することで、AI Labは「社内外を巻き込むオープンな知のハブ」としての存在感を高めています。
また、経済学的なマッチング理論を応用した「AI Lab Project Matching(APM)」という独自の仕組みも開発。プロジェクトオーナーと協力希望者が互いに優先順位を提示し、最適な組み合わせを実現することで、研究者同士・事業担当の新たな協業の種が次々と生まれています。既に約20件のプロジェクトがこの仕組みから動き出し、「自発性」と「最適配置」の両立によるイノベーションが加速しています。
これら全て、「AI Labあした会議」において自分たちで発案し実行に至った案となっており、必要な制度を自ら立案することが可能なことが特徴です。
AI Lab発イノベーションの広がりと、これから
AI Labの独自カルチャーや仕組みは、着実に組織の枠を超えて波及しつつあります。
社内の各事業部との共創だけでなく、外部パートナー企業やアカデミアとの共同研究・共創プロジェクトも増加。研修委員会が提供する学びのコンテンツや研究プロセスも、外部に向けて積極的に公開され、業界全体のベストプラクティスづくりにも貢献し始めています。
また、「研究成果=論文」だけではなく、「社会実装=現場の価値創造」が当たり前となった今、私たちAI Labは、従来の「専門分野ごとの壁」もさらになくし、横断的な知見融合によってインパクトの最大化という次なる挑戦へと踏み出しています。
AI Labが挑戦の最前線で体現しているのは、「技術」×「事業」×「人」の掛け合わせによる、持続的イノベーションの組織モデルです。この現場の熱量と仕組み設計の両輪が、これからの「AI時代」に不可欠な企業戦略のロールモデルとなることを目指します。
今後もAI Labは、制度と自発性、閉じずに広げ続ける仕組み、そして“実装”へのこだわりを武器に、持続的に社会へインパクトを届けるとともに次のイノベーションの種を育んでまいります。
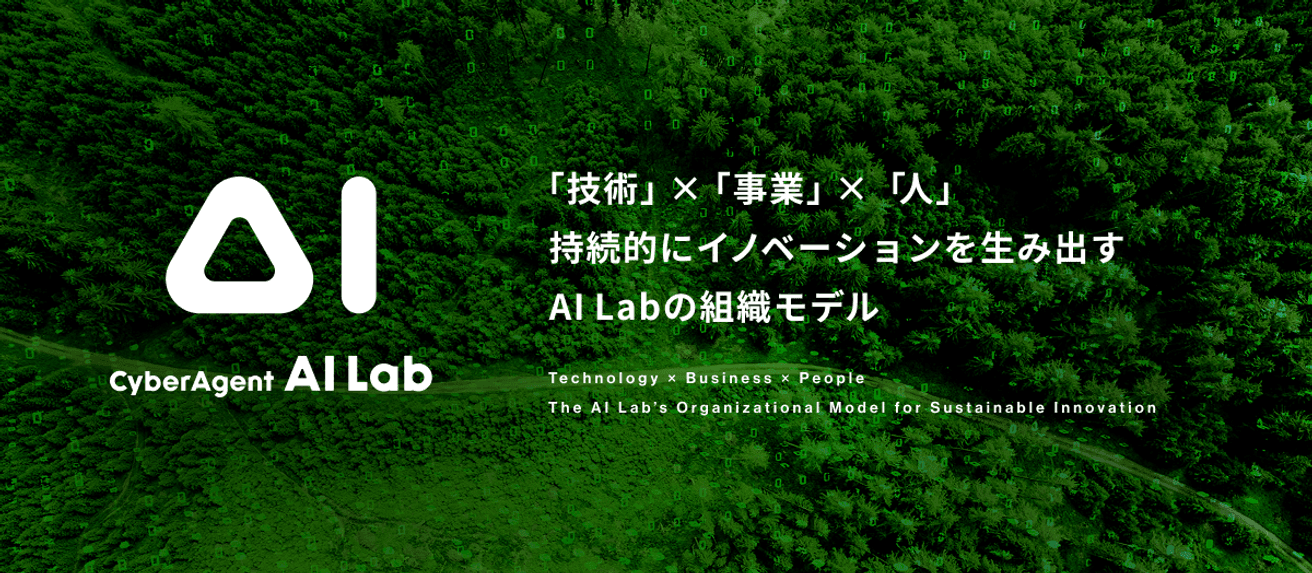
記事ランキング
-
1

サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像
サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像
サイバーエージェント2代目社長 山内隆裕のキャリアと人物像
-
2

Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ
Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ
Jリーグ百年構想リーグ開幕!世界で戦うビッグクラブへ
-
3

社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社...
社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長から2代目への社長交代
社長交代を重ねても持続的に成長する会社になるために 創業社長...
-
4

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...
【対談】ML/DSにおける問題設定術
~ 不確実な業界で生き抜くために ~

機械学習やデータサイエンスがビジネスの現場で当たり前になりつつある今、求められているのは、ビジネスの課題を実装に落とし込み、運用し、継続的な価値を生み出す視点となりつつあります。
サイバーエージェントでは、こうした実践的なスキルを持つ次世代のデータサイエンティストを育成すべく、2025年11月、新卒向け特別プログラム「DSOps研修2025」を実施しました。
「技術を社会実装する際の『問題設定』こそが重要である」 この研修のコンセプトに深く賛同いただき、特別講師としてお迎えしたのが、半熟仮想(株) 共同創業者であり、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」にも選出された齋藤優太氏です。
第1部では、半熟仮想(株) 共同創業者であり、Forbes JAPAN「30 UNDER 30」に選出された齋藤優太氏をお招きし、「ML/DSにおける問題設定術」について講演いただきました。 続く第2部では、齋藤氏に加え、当社執行役員兼主席エンジニアの木村、AI Lab リサーチサイエンティストの暮石が登壇。「現場視点×経営視点」でパネルディスカッションを実施しました。
本記事では、白熱した第2部「パネルディスカッション」の模様をダイジェストでお届けします。



