20代で営業統括、30代で専務執行役を務める石田が考える、しなやかなキャリアの築き方

2021年度よりガバナンス強化を目的に、経営の監督と執行を明確に区分した当社の新しい執行役員体制。「次世代抜てき枠」として、社長の藤田などと共に本体役員室に入り、専務執行役員に就任した2004年入社の石田裕子をご紹介します。
目次
入社以来、広告事業統括として営業最前線、「Ameba」のスマホシフト立ち上げ、2社の子会社社長、人事採用執行役員など幅広い経験を持つ石田。それは、得意分野のみに逃げ込むことなく挑戦を続け、しなやかにキャリアを築いてきた証です。
しかし、そんな彼女は今回の就任に対して「実績の評価ではなく、期待を込めての選出です」と話します。
では、20代で営業統括・30代で専務執行役員を務め、プライベートでは2児の母である石田が、経営陣から期待され続ける理由とは。

2004年新卒入社。広告事業部門で営業局長・営業統括に就任後、Amebaプロデューサーを経て、2013年及び2014年に2社の100%子会社代表取締役社長に就任。2016年より執行役員、2020年10月より専務執行役員に就任。人事管轄採用戦略本部長兼任
「女性活躍」はダイバーシティを進める上での第一歩
──専務執行役員としての役割を教えてください。
大きく3つありますが、1つは活躍人材を育てることです。
なかでも、「女性活躍推進」が私の大きな役割だと思っています。
──政府が女性管理職3割の目標を掲げてから久しく、多くの企業にとっても課題となっていますね。
他社同様、サイバーエージェントでも女性幹部候補人材の育成に今まで以上に注力しています。
すでに幹部候補となっている人材の育成は勿論のこと、いまだ顕在化していない「活躍ポテンシャル層」と言っているんですけど、その人たちの強みを伸ばしていきたいと考えています。
──多くの社員の可能性を見出そうとしているのですね。
これは一つの事例としてですが、私自身、これまで大きな部署異動や、子会社の代表取締役、執行役員というような「新しい役割への挑戦」を何度も経験したことで、成長できたと思っています。
そのたびに大きな失敗も沢山しているのですが、毎回、与えられた役割の意義を自分なりに考え、期待以上の成果を目指す、というサイクルを徹底してきた自負があります。
この”自分なりに解釈して行動する”ことはキャリア形成において大事だと思うんです。

──自分の役割がどう事業貢献に繋がっているのか、これを意識すると仕事の仕方は変わってきそうです。
そうなんです。事業に貢献していると感じると、それが原動力にもなります。
だから、女性活躍に本当に必要なのは「継続的にチャレンジする環境」だと思っています。
そのチャレンジは管理職でもいいし、プレイヤーとして自分の業務を極めるプロフェッショナルでもいい。また、その二者択一だけでもありません。人それぞれでいいし、時期によって変わってもいいんです。
重要なのは、自らの意思で、自分のスキルアップ、キャリアアップを目指し、“チャレンジ”をすること。
成功も失敗も含めて全ての経験が糧となって、結果的に本人の成長や活躍につながるんだと思います。
社員の可能性を発見→チャレンジの機会を創出→うまくいけばさらなる挑戦の場を提供。
このループを数多く生み出すことで、女性活躍を推進できればと思っています。
──ライフイベントにキャリアが左右されやすい女性は、知らず知らずに自らのチャンスに制限をかけてしまっている人もいるかもしれません。きっかけを与えてもらうことで気付くことも多そうです。

先日、働く女性の約7割が「現状維持」か「幹部職にはなりたくない」と答えたという調査※がありました。「家庭内や組織のサポート不足」を課題として感じている人が多く、周囲のサポートに加え、男女間の意識・価値観の改革が必要なことは明らかです。
サイバーエージェントには、「挑戦と安心はセット」という人事制度設計の上で大事にしている概念がありますが、挑戦できる環境と安心できる環境が両軸で備わることで人材の活躍支援につながります。
その環境を活かし、様々な価値観・志向性の中で、女性が前に進める仕組みをつくっていきたいです。
※LinkedIn「日本女性の仕事と生活に関する意識調査」
抜てきの仕組みを複数用意することで、若手活躍が加速する
そしてそれは女性に限った話ではなく、様々な活躍の在り方やキャリア形成があることが、社員にとっても会社にとっても明るい未来に繋がると思っています。
活躍人材の輩出という役割において、チャレンジの機会を創出し、抜てきのバリエーションを複数持つことで、「若手の才能開花」にも貢献していきたいと考えています。
──当社には「環境が人を育てる」という考え方もありますね。
はい。若手育成と同時に、私たち育成する側が”現代の”働き方や価値観の変化をきちんと認識しなくてはいけないと思っています。
──”現代の”働き方とは?
働き方改革が進み、労働時間が評価に直結しない時代。若手であっても生産性高く成果を上げられる仕組みが必要です。
これまでの常識に囚われず、様々な価値観や考え方や個性を取り込んでいくべきだと考えています。
──育成する側も変わらないといけないんですね。
育成側に”当たり外れ”があってはいけませんし、そのほうがもっと若手の才能開花が進むと思います。
育成する人も育てる、それが若手活躍を加速させる大きな要素です。
”サイバーエージェントらしい”人材採用と働き方の創出
2つ目は、採用の責任者として継続的に「良い採用」をしていくことです。
将来のサイバーエージェントを率いていける人をたくさん輩出する。そういう人材が出てきてはじめて「良い採用」と言えます。
──「良い採用」だったかどうか、その答え合わせには何年も時間がかかるのですね。
採用という仕事は採用して終わりではなく、採用した人材が才能を開花させ活躍する、これに尽きるんです。中長期的な視点で、未来のサイバーエージェントを担える「良い採用」を推進していきたいと思います。

そして3つ目は、「会社のカルチャーを犠牲にしない働き方」を創っていくことです。
今年の4月、コロナ禍に「次世代ワーク推進室」という、これからの働き方を考え、推進していくプロジェクトを新設し、その責任者となりました。
現時点での「次世代ワーク推進室」のゴールは、リモート環境であっても熱量の高い組織つくること。
この先、新型コロナウィルスの感染拡大が収束したとしても、もう元の働き方には戻れないことは確かです。
世の中を賑わせている「ジョブ型」、「メンバーシップ型」の両方のいいところ取りをしながら、サイバーエージェントらしい一体感や熱量を保ち、成果に集中できる環境づくりに取り組んでいければと思っています。
女性活躍の礎となるために、さらなる成果を
私は2004年に新卒で入社して以来、山あり谷ありの経験を重ね、とにかくずっと変化の中に身を置いてきました。人一倍失敗も経験しているんですけど、どんな状況でも絶対に逃げずに最大限のパフォーマンスを目指してきた、これだけは自信を持って言えます。
その結果、ありがたいことに何度も抜てきの機会をもらってきました。
また、「あした会議」など経営陣と議論する場をたくさん経験したことで、彼らとの圧倒的なレベル差を早期に気付けたんです。
そのおかげで、早くから全社経営視点を持つことができた。これが今回の選出に繋がるのかもしれません。
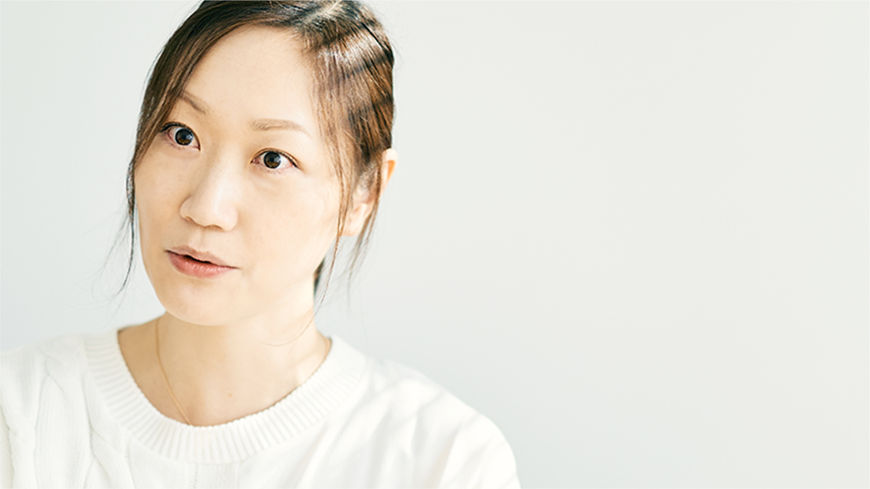
アメリカ初の女性副大統領、カマラ・ハリス氏の「私は最初の女性副大統領かもしれませんが、最後ではありません」という演説がありましたが、サイバーエージェントにおける女性の抜てきも、当然私が最初で最後ではありません。
今回の選出をきっかけに、1人でも多くの社員が「私も役員を目指してみよう」と思ってもらえたら嬉しいな、と。その分、次に続く社員のためにも私のところで躓くわけにはいかないという、かなり重いプレッシャーを感じていることも事実ですが(笑)
サイバーエージェントが、名実ともに女性が活躍できる会社になっていくために、これまで以上に、期待値を超えるパフォーマンスを出せるよう尽力していきます。

記事ランキング
-
1

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来
アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来
アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと...
-
2

クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェントが支援する「...
クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェントが支援する「AI×制作プロセス改革」の最前線
クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェ...
-
3

企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的AIリーダーが語...
企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的AIリーダーが語る最先端戦略「AI SHIFT SUMMIT 2025」開催へー
企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的...
-
4

世界に響くIPを創出へ サイバーエージェントのアニメ&IP事業戦略の全貌
世界に響くIPを創出へ サイバーエージェントのアニメ&IP事業戦略の全貌
世界に響くIPを創出へ サイバーエージェントのアニメ&IP...
三菱UFJ銀行との協業から生まれた
「信頼でつなぐ広告 Bank Ads」
テクノロジーと倫理が交差する、広告DXの実践

2023年、三菱UFJ銀行とサイバーエージェントは、金融データと広告技術の融合による新たな広告事業「Bank Ads」を立ち上げました。
信頼性を前提とした広告のあり方が問われる時代において、銀行が保有する1st Party Dataと、広告業界で培われた開発・運用ノウハウを掛け合わせ、安心かつ効果的な広告体験の実現に挑んでいます。
本記事では、プロジェクトの中心メンバーである杉山・伊藤の両名が、「Bank Ads」の誕生背景や具体的な開発プロセス、信頼と成果の両立を目指すための思想や仕組み、そしてテクノロジーとビジネスの境界線を越えたキャリア観について語ります。



