大ヒットを生み出し事業を成長させる
熾烈な競争環境を勝ち抜くためのマーケティング組織に迫る
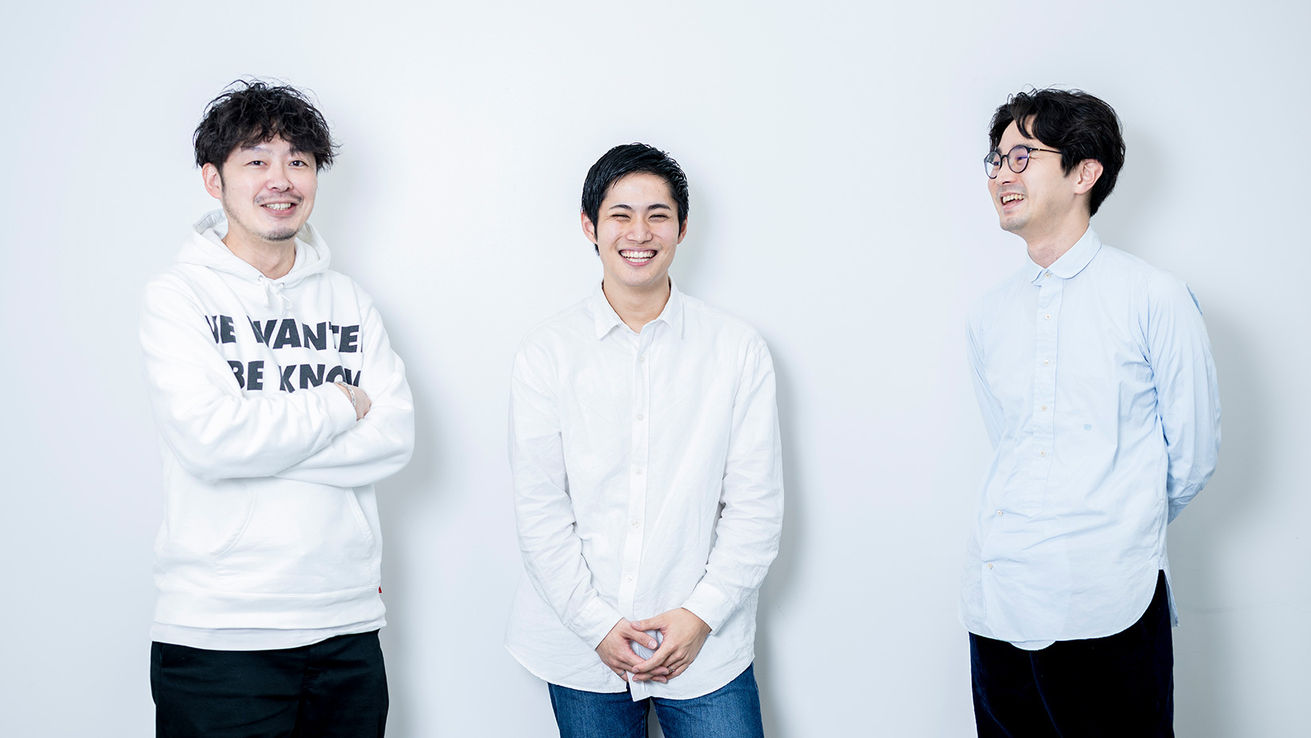
日本のゲーム市場は1兆7330億円を超え、世界第3位と非常に大きい市場です。当社のゲーム事業はスマートフォンゲームにおいて業界最大規模のシェアを誇りますが、市場が成熟してきた今、継続的なヒットを生み出せるか否かが非常に重要になっています。
そんな中ゲーム事業部では、マーケティングに注力するため、執行役員 副社長の指揮のもと、ゲーム子会社横断のマーケティング組織「SGEマーケティング本部」を強化。今回は同組織の3名のボードメンバーに、設立背景やミッション、実際の業務内容について話を聞きました。
Profile
-

株式会社グレンジ 取締役
関根 悠二
2011年サイバーエージェント新卒入社。
グレンジ創業期にプロデューサーを経験した後、株式会社グリフォンの立ち上げに取締役として参画。
複数社の立ち上げを経験後、グレンジに戻り運用タイトルのプロデューサーを担当。
2017年にSGEマーケティング本部を立ち上げ、現在は戦略マーケティングの推進責任者を務める。 -

株式会社サムザップ プロダクトマーケティング室 室長
原田 隆太
サイバーエージェント広告事業本部にてアカウントプランナーとして従事後、ゲーム会社に転職し、ゲームやマンガアプリのマーケティングに携わる。
2016年にサムザップに入社。『戦国炎舞 -KIZNA-』や『この素晴らしい世界に祝福を!ファンタスティックデイズ』、『D_CIDE TRAUMEREI』などのマーケティングに従事。現在はプロダクトマーケティング室の室長とSGEマーケティング本部にて、大規模プロモーションのサポートを担当。 -

株式会社アプリボット マーケティング本部
グローバルパートナー事業部 広告責任者
及川 泰司
2018年サイバーエージェント新卒入社。
株式会社アプリボット グローバルパートナー事業部に立ち上げから携わり、日中韓のゲームアプリクライアントの広告責任者を複数担当。
現在はSGEマーケティング本部にて、新規タイトル立ち上げ推進も担当。
SGEマーケティング本部とは?
──SGEマーケティング本部について教えてください。

関根
ゲーム・エンターテイメント事業部は株式会社Cygames以外の10社以上の子会社で構成されており、その子会社群を総称してSGEと呼んでいます。
SGEマーケティング本部は、各子会社に所属するマーケター全員が所属している横軸のマーケティング組織です。

関根
「マーケ8」と呼ばれるボードメンバーがそれぞれ注力すべき分野を決め、会社の垣根を超えて相談できる体制をつくっています。
例えば私の場合は戦略マーケティングの責任者として、事業を伸ばすための戦略を立てるサポートを担当しています。及川は、新規タイトルの立ち上げサポート、原田は大規模プロモーションのサポートといった具合です。

関根
熾烈をきわめるマーケットで、自社プロダクトの成功角度をあげるためです。
以前は事業部専属のマーケターがおらず、サイバーエージェント全体のマーケティング組織がプロジェクトに応じてスポットで担当していました。しかし、市場環境が激化、闘う市場が世界へと広がり、開発費用が膨大になってきたため、各子会社ごとに専門性をもったマーケターを立てるようになりました。
そこから連携を強化するために、横軸組織であるマーケティング本部を設立するようになったのが今から3年ほど前です。
──同じグループ会社とは言えライバルでもあると思うのですが、横の連携を強化する理由はなぜでしょうか?

関根
もちろん切磋琢磨するライバル関係であることは変わりありませんが、“事業を伸ばす”ためにマーケティングをしているので、そこのノウハウを共有することで全体のボトムアップができるというのは、全ての会社にとってプラスに繋がると考えているからです。
マーケティングと一口に言っても、プロダクトのターゲットやフェーズによっても手法は異なります。
トレンドの移り変わりが激しい中で最新トレンドをキャッチアップして実行していくには、各子会社での経験を横展していくのがもっとも効率的ですし、やるべきだという思想のもと、会社を超えてお互いナレッジを共有できる組織文化を醸成しています。

関根
いいプロダクトをつくって売る、そして「ネット広告に強い」から「マーケティングに強いSGE」を目指していくために組織として注力していこうというゲーム事業担当役員の日高からのメッセージです。
サイバーエージェントは設立当初から広告事業をしているので、SGEもネット広告を得意としている組織です。
ただ、タイトル数も多く、クオリティも高く、競争が激しい現状では、ネット広告の強みを活かすだけでは、新規ゲームが埋もれる可能性が非常に高くなっています。


関根
プロダクトがいいのはもちろんのこと、ユーザーに手にとってもらう仕掛けをいかにつくれるかが重要です。
想定ユーザーを選定し、そのユーザーに刺さるプロモーションを考え、そこにネット広告の強みを掛け合わせていくといった「WHO(誰に)WHAT(何を)HOW(どうやって)」を徹底して突き詰めていくようになりました。

関根
上述したノウハウ共有ができる文化はもちろん、経験量が強みだと思います。
1200名規模のゲーム開発組織でマーケターは60名程在籍しているので、数名のマーケターの組織と仮に比較したとしても、経験の量が多いのではと思っています。
常にPDCAが回っているので自社内で生きたノウハウが蓄積され、伝播していくのは強みだと思っています。
やりがいは“経営直結”と“インパクトの大きさ”
──現在どのような仕事をしているのでしょうか?

及川
海外で制作されたアプリの日本展開や、社内プロダクトが海外展開をする際のマーケティングを担当しています。

及川
いや、実は全然そんなことはなく、新規事業をやりたいと思ってゲーム事業を志望しました。その時に新設されたのが現在所属しているグローバルパートナー事業部で、そこに配属をされました。

──入社時から成長したと感じることは?

及川
「自分事化するスキル」が身についたと思います。
マーケティングは経営と直結した仕事で、マーケティング次第でプロジェクトそのものがなくなってしまったり、会社の経営が落ち込んでしまう可能性ももちろんあります。
なので、日々どんなことでもこの仕事がどんな影響を及ぼすのかを考える癖がつきました。

及川
ある企業のマーケティングをサポートした時ですが、そこの企業のゲームの売上次第で会社の経営状況が変わるという案件がありました。ゲームはとにかく初速が肝です。そのため、どのように訴求していくのかを定量・定性の調査データで仮説を立て戦略を組んでいきました。
結果、目標以上のインストール数を大幅に達成、経営もV字回復したという事例があり、その時に経営と直結していることを強く感じました。
自分の立てた戦略次第でプロダクトを成功に導くことができる、そこにやりがいを感じています。
IPタイトルとオリジナルタイトルの違いは?
──主にIPタイトルのマーケティングに携わっているとのことですが、オリジナルタイトルとマーケティング手法に違いはありますか?

原田
まず、IPタイトルには既にそのIPのファンがいます。そのため、既存ファンが自分たちが好きなIPがゲームになるにあたり、どんなインサイトがあるのかを考えるのが大事だと思います。
そして、IPの世界観を壊さずに、忠実に寄り添いつつマーケティングを考えるというのが一番の違いだと思います。
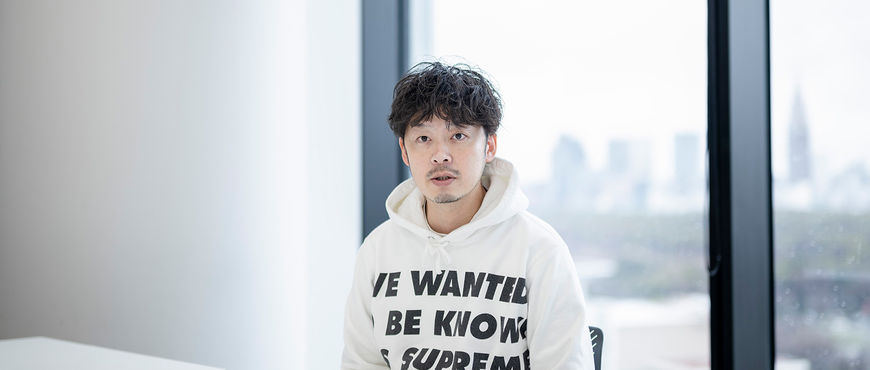

原田
IPのファンはそもそもどういった人なのか、その中でもゲームをする層はどんなユーザーなのか、どんなインサイトを持っているのか、何がゲームをプレイするための武器になり、障壁になるのか。
それらを仮説検証していきつつ、そのようなターゲットに対してどのようなアプローチをしていくかを考えていきます。

原田
一番はファンからダイレクトに大きな反応がくることです。オリジナルタイトルは1から全てを積み上げていきますが、IPだと既存ファンがすぐに反応してくれるので、そこは面白いですし反響の大きさを感じます。大切なIPをお預かりしているという責任感も改めて感じます。
また、IPのステークホルダーと一緒に1つのプロジェクトとして進めていくので、関わる人が多いです。交渉や調整など大変なこともありますが、その分自身のビジネススキルも成長実感を得やすいです。
大ヒットを生み出し事業を成長させる
マーケティング本部のこれから
──昨年より強化しているマーケティング本部で、チャレンジしていることはなんでしょうか?

関根
消費財メーカーなどで実績のあるマーケティングスキームをどんどん取り入れていて、戦略の確認と顧客理解に力を入れるようになりました。
これまでのゲームづくりはある意味では、プロデューサーのセンスに任される領域だったのですが、投資予算が増えている分、品質として市場レベルを超えていくために、インタビュー調査による顧客理解を推進するようにしています。

原田
機能による差別化が難しい業界で、ゲーム事業もそれに近しくなってきたからです。
プロダクトがいいのは当たり前な業界で、いかに選ばれるプロダクトをつくって選んでもらうか。とにかくヒット確率を上げていくことを心がけています。

原田
関われるマーケティングの分野が広いことだと思っています。
戦略設計から調査、戦術策定、デジタルマーケティング以外にも、オフラインでユーザーと接点を持つイベント、テレビCMや交通広告など。IPタイトルだとより多角的に展開しやすいので、グッズ展開や、ゲーム以外の異業種とのタイアップができたりなど、プロモーション手法も無限です。

及川
私が感じるのは反響がすぐに出ることだと思っています。
アップデートなどの施策1つでもリアルタイムで反響が出るので、より早いPDCAを回せるのはいいですよね。

関根
大ヒットプロダクトをつくるためにマーケティング組織があるので、ヒットプロダクトをつくるのと、それを継続させていくことのできる組織にしたいと思っています。
また、若手がマーケティングスキルを習得できる機会を増やしていきたいと思っています。マーケティングは市場を生き抜くための普遍的なスキルだと思うので、ゲームマーケティングを通してそういったスキルを身に付けられる組織にしていきたいです。
記事ランキング
-
1

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来
アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来
アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと...
-
2

クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェントが支援する「...
クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェントが支援する「AI×制作プロセス改革」の最前線
クリエイティブ制作の変革が、経営を変える。 サイバーエージェ...
-
3

企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的AIリーダーが語...
企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的AIリーダーが語る最先端戦略「AI SHIFT SUMMIT 2025」開催へー
企業成長の鍵となる「AIエージェント革命」の始まり ー世界的...
-
4

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...
三菱UFJ銀行との協業から生まれた
「信頼でつなぐ広告 Bank Ads」
テクノロジーと倫理が交差する、広告DXの実践

2023年、三菱UFJ銀行とサイバーエージェントは、金融データと広告技術の融合による新たな広告事業「Bank Ads」を立ち上げました。
信頼性を前提とした広告のあり方が問われる時代において、銀行が保有する1st Party Dataと、広告業界で培われた開発・運用ノウハウを掛け合わせ、安心かつ効果的な広告体験の実現に挑んでいます。
本記事では、プロジェクトの中心メンバーである杉山・伊藤の両名が、「Bank Ads」の誕生背景や具体的な開発プロセス、信頼と成果の両立を目指すための思想や仕組み、そしてテクノロジーとビジネスの境界線を越えたキャリア観について語ります。


