大切なのは自分ならではの価値を出すこと。
できない自分に向き合った1年目を振り返る
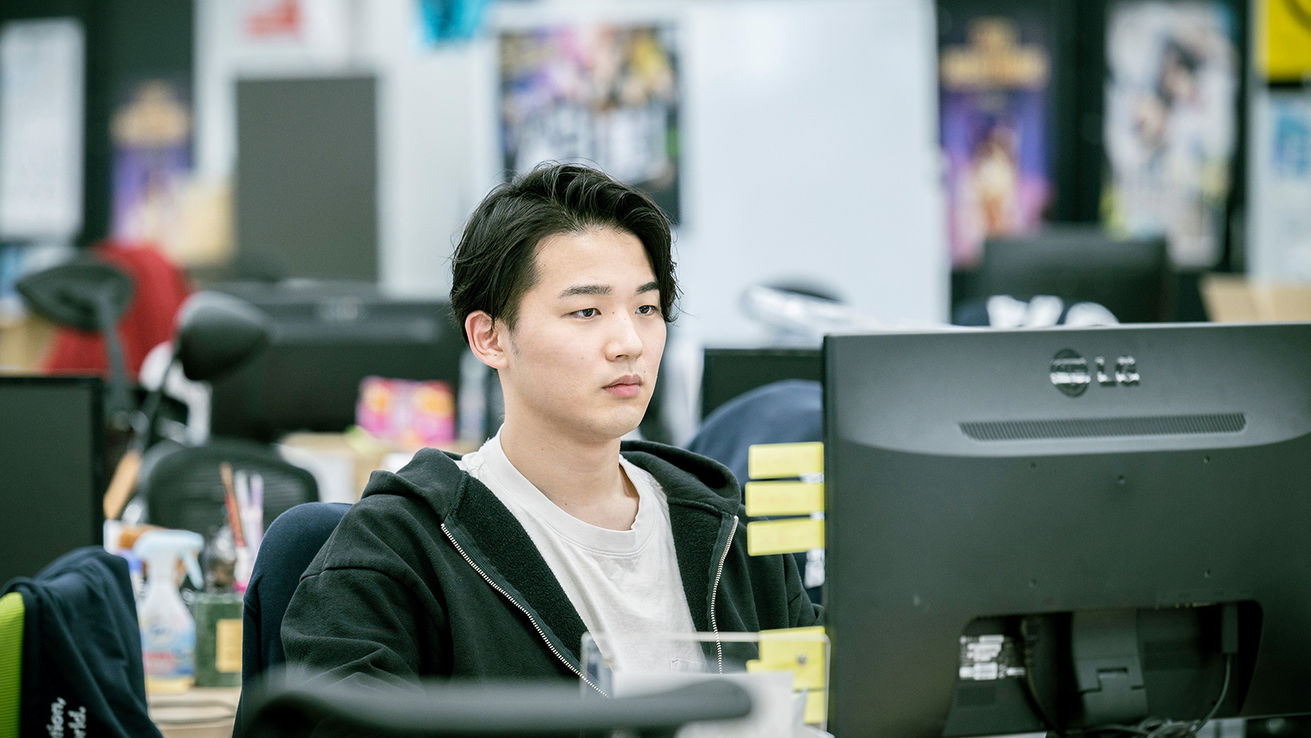
2020年4月1日、217名の新入社員が入社してから早1年が経とうとしています。新型コロナウイルスで入社直後の新卒研修はフルリモートで実施、その後も状況は変わらず1年の半分以上をリモートで過ごした20卒新卒。
そんな前例のないスタートとなった彼らの1年間は何を経験し、どのような成長を遂げたのか。新卒1年目を振り返ります。
Profile
-

株式会社AJA
安藤 航太
2020年サイバーエージェント新卒入社。入社直後から新販路の立ち上げにセールスとして参加。2020年度下半期の全社グッドスタート賞ノミネート。10月以降からは新プロダクトの立ち上げプロジェクトに参加するなど、社内において様々なポジションを経験。4月よりグローバル顧客のフロント及び開発ディレクションを行う。
動画広告に特化した広告プロダクト
AJAでの仕事は?
──AJAについて教えてください。

安藤
「ABEMA」や「Ameba」などを管轄しているサイバーエージェントのメディア事業部から生まれた2016年設立のアドテクノロジー会社です。これまでのメディア運営において培ったノウハウと技術力を強みに最先端の広告プロダクトを開発・提供し、媒体社の収益向上支援と企業のマーケティング支援を行っています。
なかでもここ数年AJAが注力しているのが、動画広告プラットフォーム事業です。特にコロナによる巣ごもり需要で動画配信サービスの利用者が増えたことで、多くの企業のプロモーションにおいて動画広告の活用が進んでいます。
──入社してからのキャリアを教えてください。

安藤
入社直後は新規販路の立ち上げチームで営業を担当し、現在は新しい広告プロダクトの立ち上げと営業を担当しています。
この新規プロダクト立ち上げでは、代表の野屋敷を筆頭にベテラン社員ばかりの中に自分も参加させてもらい、毎日刺激を受けながら仕事に励んでいます。
──1年目から新規プロダクトに関わるのはすごいですね。仕事を進める上で大変なことはありませんでしたか?

安藤
キャリアも知識も豊富なメンバーに囲まれ、新規プロダクトにも携わらせてもらい非常に光栄だったのですが、変に萎縮してしまって手が止まってしまったことがありました。
営業の時は目標とする数字が明確なため、試行錯誤もしやすかったのですが、新しい取り組みで正解がわからない中で自分が何をすべきかが見えず指示待ちの状態になってしまいました。
その悩みをトレーナーに相談したところ「自分で考えて本当に必要だと思ったら勝手に進めてしまえばいい。本当に駄目なことは周りが止めるから、全部やってしまうくらいの気持ちでいこう」とアドバイスをもらい、萎縮して止まってしまうのは無駄だととにかく前に進むことを意識するように。
そこからは“仕事を自分で作る”ことを心がけていました。
──具体的に何を変えたのでしょうか?

安藤
そもそも止まってしまった理由は自分の中でゴールが明確でなかったことが原因だと気付き、目標の解像度を上げました。
理想状態できるだけ細かくイメージし、そこから逆算して今何をすべきなのかを考えることで、具体的な行動に移せるようになりました。
この経験からも、「目標の解像度を上げる」というのを仕事で最も大切にしています。ゴールさえ明確になっていれば、たとえ仮説通りに進まなかったとしても別ルートを考え直せばいいのでいろいろな打ち手を考える事ができます。


安藤
また、進めていくにあたりトレーナーとの細かい報・連・相を徹底し、逐一方向性をすり合わせるようにしていました。リモートで顔が見えない分、自分が今何をしていて、何に困っているのかというのをオープンにするように心がけていました。

安藤
よくサイバーエージェントでは「青い炎」と「赤い炎」という言葉で比較されるんですが、AJAは「青い炎」な人が多い組織だと思います。つまり、淡々としているように見えるけれど、内側の闘士が熱いという方が多い気がします。
また、「背中を預けられるチームをつくる」というミッションステートメントがAJAにはあり、チームで連携したり、お互いが協力しあうカルチャーが根付いています。スタートアップなので任せてもらえる領域も広いのですが、やり方は本人に任せつつも、いざという時は手を差し伸べてもらえるような、信頼関係があるからこそ成り立つ絶妙な距離感がAJAの組織の魅力の1つだと思います。

安藤
社内のミーティングも商談も、その多くがZoomの画面越しだったので、打ち合わせに参加している人の反応やその場の雰囲気が掴みづらかったです。
コミュニケーションが円滑な方が仕事は進めやすいと思うのですが、最初はドライなやりとりしかできず苦労しました。

安藤
勇気を持って雑談をふることです(笑)。
提案の論理的な正しさや具体的なメリットも大事なのですが、「この人の話だったら聞こうかな」と思ってもらえるような関係性がとても大切だと感じています。小さなことでも相談しやすい関係性をつくり、必要な情報を滞らせないようにするということを意識していました。
仕事は人と人が関わって成立するものなんだと、特に感じた一年だった気がします。
全社にインパクトを残したい
AJAで働く理由
──なぜAJAで働こうと思ったのですか?

安藤
学生時代に1年間休学をして、とあるベンチャー企業でエンジニアとして働いていたことがあります。そのため、他のビジネス職の同期と比べてテクノロジー領域の知識があることが自分の強みでした。
そういった自分の強みを活かしつつ、1年目から裁量が与えられ、早くから多くの決断経験を積むことができるスタートアップで挑戦したいと思い、アドテク系子会社であるAJAで働くことを決めました。AJAが動画広告という大きな市場にチャレンジをしていたことも要因のひとつです。
──ベンチャー企業で働くことになった経緯は?

安藤
就活当初は総合商社や不動産などの日系大手企業を受けようと考えていたのですが、偶然プログラミングを勉強する機会があり、それが想像以上に面白かったんです。そこから「エンジニアになる道もあるかもしれない」と考えるようになりました。
そのためには実務レベルでも通用するスキルを身に着ける必要があると思い、エンジニアとしてインターンを始めたという経緯です。

──なぜ休学しようと思ったのでしょうか?

安藤
初心者が中途半端にやっても、何も身につかずに終わると思ったからです。インターンシップ先の社長に「どうせやるなら、しっかりコミットして力をつけないと時間の無駄になるよ」と言われたこともあり、休学してフルコミットで働くことを決めました。
スマホアプリを開発している設立したばかりのベンチャー企業で、機能の設計から実装まで、本当に幅広く関わらせてもらいました。最初は1時間でできることに1日費やしてしまったりもしましたが、できないことができるようになっていくその過程が楽しいと思いましたし、プロダクトの責任を持つことの厳しさと楽しさの両方を経験しました。
──サイバーエージェントに決めた理由は?

安藤
優秀で、熱量の高い同世代の多さに魅力を感じたからです。
自分にないものを持っている人がたくさんいて、こんな人たちと一緒に働きたいと思ったのがサイバーエージェントに決めた理由です。
組織に対して自分は何ができるのかを考える
2年目への抱負
──この1年を振り返ってみてどんな1年でしたか?

安藤
できない自分と向き合った1年でした。
正直、入社当初は今までの経験を活かしてすぐに活躍できるだろうと思っていたんです。
しかし、実際に仕事をしていく中で経営層の視点の高さや判断スピードを間近で見て、レベルの差を痛感。自分が考えていた「できる」の基準の低さと範囲の狭さに気づきました。
最初はできない自分に悩むこともありましたが、今は学びが多く、成長を実感できることをポジティブに捉えています。


安藤
あとは、チーム全体での成果を意識するようになりました。
──というと?

安藤
もともと自分の成果のことだけを考えているタイプでしたが、チームで働く中で一人では大きな成果を出せないということに気付きました。自分一人で1の成果を出すよりも、チームで10、100の成果を出せる方が良いなと。
そのため、チームでの目標に対して、自分の価値をどう出していくかを考えて行動するようになりました。そうすると、必然的にやるべきことは明確になってくるのと、新たなチャレンジの機会も増えて成長にもつながります。
チーム全体でどう成果を残すか、そのために自分は何ができるのかをとにかく意識するようになりました。

安藤
とにかく、事業に対して自分が提供できる価値を大きくしていきたいです。
難度が高く前例のない挑戦が多い環境ですが、裏を返せば努力次第で年次に関係なく価値を生み出せるチャンスなので、成果を出すことにこだわり抜きたいと思っています。
記事ランキング
-
1

「Inbound Marketing Summit」開催レポート
「Inbound Marketing Summit」開催レポート
「Inbound Marketing Summit」開催レポート
-
2

「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・入館方法
「Abema Towers(アベマタワーズ)」へのアクセス・...
-
3

「AI Worker」と自律型AIエージェントが実現する 人とAIが協働する世...
「AI Worker」と自律型AIエージェントが実現する 人とAIが協働する世界とは?
「AI Worker」と自律型AIエージェントが実現する 人と...
-
4

アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来
アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと描く未来
アニメ制作の新時代を切り拓く「CA Soa」 クリエイターと...
「Inbound Marketing Summit」開催レポート

2025年4月24日に開催した「Inbound Marketing Summit」。急拡大するインバウンド市場ですが、効果的なマーケティング手法が確立されていないのが現状です。本サミットではこの課題に対し、TencentJapan、せーの、大丸松坂屋百貨店、資生堂ジャパンが登壇。各社の戦略を紹介すると共に、当社「インバウンド消費行動研究室」による最新の調査結果も共有しました。当日のセッションの様子を一部お届けします。



